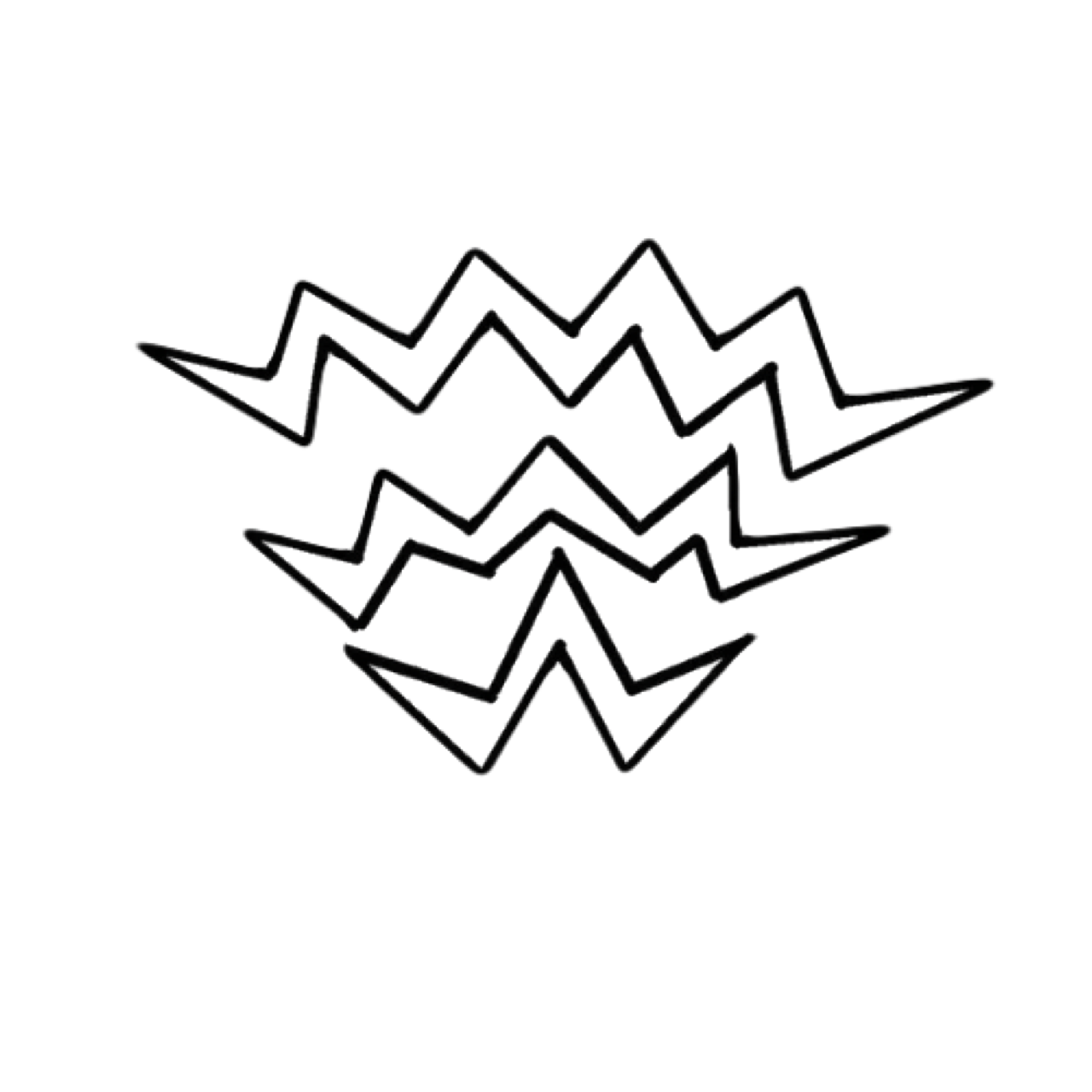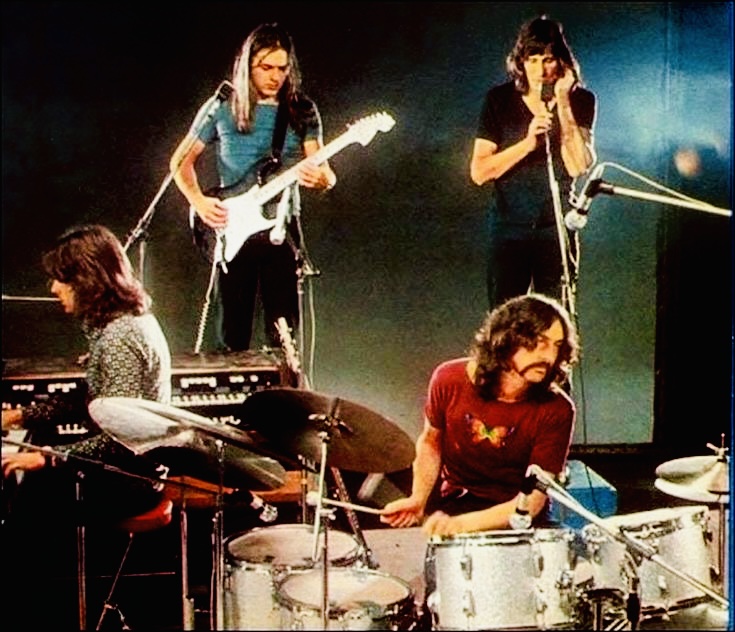
Pink Floyd 「Time」はZ世代にアンセムとして迎合されるのか
1973年の3月。燦然と輝く世紀の大名盤、Pink Floyd「The Dark Side Of The Moon(邦題「狂気」)」がリリースされる。このアルバムは人間の内面に潜む「狂気」を描き出すというコンセプトになっており、地球上で生活を営む全ての人間に普遍的に当てはまる出来事を歌っている。
しかし、リリースされてから51年も経ち、時代を経れば、価値観も変わるという言論は流布され尽くし、2000年代以降に生まれてきた筆者達にとっては何度身をもって体感してきたことか。もはや鬱陶しくうるせえと叫びたくなる。そんな疲弊感すらも持っている我々Z世代は半世紀前にリリースされた「Dark Side of the Moon」を受け入れるのか。また、20代のアンセムとまで言われている楽曲「Time」について自分達はどのように思考を巡らし、アンセムとして迎合するのか。
本記事は「Time」についてNOISE MAGAZINEのライターである柊、和氣、生の三人が語ったもの書き起こし記事にしたものだ。したがって初めに留意して頂きたい点としては、あくまで本記事はたかが20代前半の男3人の語った内容を抽出したものである。この考えが全てではなく、それを鵜呑みする事は避けて頂きたい。また、「今の若者」がこんな属性をしているのかと安易なラベリングを助長するつもりも毛頭ない。なので、本記事を読み進める前に、一度自分の中で「Time」と向き合い、今読んでいるそこの貴方はどのように考えるのか。地を固めた上で、読む事を推奨する。
したがって「Time」の歌詞と和訳を掲載した。そして、NOISE MAGAZINEの3人の意見と読んでいる貴方はどのような摩擦が起こるのか。読み進めながら、うなずくも良し。中指を立てるのも良し。読後に何かほんの僅かなことが自分の中で得れるのであれば筆者は非常に嬉しい。
まずこの楽曲の歌詞1と和訳したものを以下の通りだ。
Ticking away
The moments that make up a dull day
You fritter and waste the hours
In an offhand way
Kicking around on a piece of ground
In your hometown
Waiting for someone
Or something to show you the way
退屈な1日を埋めるばかりで時は刻々と過ぎ
君は意味もなく時間を無駄に消費していく
故郷の地を蹴って歩き回るばかりで
誰かが
道をさし示してくれる何かを君は待っている
Tired of lying in the sunshine
Staying home to watch the rain
You are young and life is long
And there is time to kill today
And then one day you find
Ten Years have got behind you
No one told you when to run
You missed the starting gun
日向ぼっこするのに疲れ
家の中で雨を見つめている
君は若く、人生は長い
だから今日も無駄にする余裕だってある
そしてある日気づく
10年の月日が経っていることに
誰も君に走り出すべき時を教えてくれない
君は出発の号砲を聞き逃したのさ
And you run, and you run to catch up with the sun,
But it’s sinking
And racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way
But you’re older
Shorter of breath
And one day closer to death
君は走って、走って太陽に追いつこうとするが、
太陽は沈んでいく
そして、君の背後に再び現れ、君を急き立てる
太陽は変わらないが
君は歳を取り
息も短くなり
そしてある日、死が迫ってくるのさ
Every year is getting shorter
Never seem to find the time
Plans that either come to naught
Or half a page of scribbled lines
Hanging on in quiet desperation is the English way
The time is gone, the song is over
Thought I’d something more to say
1年はだんだん短くなり
「その時」というものは見つかりそうもなく
計画は無に帰するか
半ページ程に書かれた殴り書きの線になるか
静かに絶望にハマり続けるのは英国流だ
時は過ぎ、歌は終わる
もっと言いたいことがあったのに
Home, home again
I like to be here when I can
When I come home cold and tired
It’s good to warm my bones beside the fire
Far away across the field
The tolling of the iron bell
Calls the faithful to their knees
To hear the softly spoken magic spells
故郷へ、再び故郷へ
出来る限りここにいたい
凍え、疲れて帰ってくると
火の側で身体の芯から温まろう
遥か彼方から
鉄の鐘の音が鳴り響く
敬虔な人々をひざまずかせる
優しく語りかける魔法の言葉を聞かせる為に
柊:まず最初に、歌詞に入るまでのイントロだけでも俺は思うとこがあ
ってイントロが3分くらいで相当長いじゃん
生:歌詞が入ってくるのが2分20秒くらいかな
柊:2分20秒ぐらいのイントロってさ、今の時代はPinkpantheressとかが出
てきてから2分の曲とかざらにあるじゃん。 こういう時代に生きてる自分達からすると、やっぱイントロの短い曲が多いしさ、なんでそうなったかって頻繁に言及される事としては、Youtube ShortとかTik Tokの台頭によって、短い時間での刺激を一向に摂取してくみたいな 流れがあるよね。
短絡的な刺激によって、最低限の快楽を得れるツールとしてそういうのが成り立ってるわけじゃん。
生:音楽で言うならイージー・リスニング。映画とかだったら倍速視聴みたいな感じで俺らの世代はタイパを凄い気にしてるって言われてるよね。
柊:そうそう。それで俺が思ったのは、自分たちは現実世界では何もする気にならないのに、 他方その現実世界においては何もしないことが出遅れてるっていうよりか、まだ何も出来てないのに急に刺激のある世界に放り出されるみたいな 感覚があるよね。予期せずスタートが始まっちゃってる。この曲でも言ってるけど、もはやその綿密に作り上げられた人生のカタルシスみたいな部分に行く前に、短絡的な刺激にずっと晒されることによって、どこが頂点かわからないまま、 消費財としてただ自分がこう永遠と最低限の快楽の中を歩いていくみたいなとこになってるっていうのを感じてて。
で、逆にこの楽曲はイントロがありえないぐらい長いから、時の流れと存在をすっごいこっちに強く想起させる。でも快楽はまだそこには無いわけじゃん。その快楽の無いところを動き続ける。その中で自分の本当の正解みたいなものを見つけ出していくっていう体力とか忍耐力みたいなものが自分に、そして俺ら世代にあるのかっていうのをイントロだけですごい考えさせられるよね。
柊:あとは、楽曲の構造で言うとこの曲はストーリーテリングで、6分を人生で例えて、時が過ぎいつか終わってしまうっていう流れの中でちょうどイントロの2分ってティーンネイジャーぐらいまでみたいな。この世に自分として出ていくまでのティーンみたいな期間って、実は何もない時間がただ流れてる。
生:確かに、楽曲単位で見ても一つの人生として見立てることはできるかもね。でも「Dark Side of the Moon」のアルバム自体が一つの人生として俺は見立てる事が出来ると思ってて、一曲目の「Speak To Me」では主人公はお母さんのお腹の中にいる胎児で、母親と胎児で共鳴する鼓動音がするんだけど、途中から振り子時計の音(時間)、人の会話(人間関係)、レジスターと小銭の音(金)、そして最後にこれらをまとめた「狂気」に満ち溢れた外の世界に生まれる事を歓迎するかのような男の人の不気味な笑い声が入ってきて。
そして次の「Breathe (In the Air)」では、曲名からして分かると思うけど、主人公は生まれて外で初めての呼吸をする。一曲目と繋がっててこの楽曲は産声から始まって、歌詞から見てもお母さんがまだ小さい主人公に話しかけてるみたいな感じだから、主人公は未だ何をするにも親元から離れる事ができない年齢なのかなって思う。
生:それで次の「On the Run」はそれこそさっき柊が言ってたタイムのイントロみたいな感じかな。幼少期とかティーンの時代だと思う。母親とか家族の元から少し離れて生活するようになって、少なからずここから「社会」というものを経験するんだけど、もうこの時っていきなり放り出されて何も分からない。右も左も本当に何も分からず、迷いながらただ主人公が息あげて走ってる。だからこの曲は詞もなく、ティーンを駆け抜けてるっていうのもあってインストだけ。実際にこの楽曲は主人公が走る足音が聴こえるよね。2
それで今話してる「Time」に繋がるんだけど、この曲はティーンを駆け抜けてある程度社会で生きていく術を身につけて独り立ちできる能力があるのに、故郷で散歩だけして家で雨を眺めて、みんなが進んでいく中1人取り残され、ただ時間を消費しているっていう。俺は常にこの曲が(大学)一年生の頃から頭の片隅にあり続けてて、でもこの曲は俺たちの世代にだけ刺さるんじゃなくて、動きたいけど動かない、時間を無駄に消費するっていう事はどの時代の俺らには普遍性を持って聴かれるのではないのかなって思う。
柊:でもこれは俺らの世代にも強く出るんじゃないかなって。というのも失われた30年が日本にはあって、バブル崩壊以降の日本の閉塞的な状況が強くここには関係してるかな。俺ら、失われたって言われてる時間しか生きてきてないからそれこそ先が見えない感じとか、 自分たちの生活は確かに回ってるかもしれないけど、それが何かに向かっているのか一切わからない状態。経済的にも、政治的にも、やっぱ俺らの生きてる時代っていうのは、そのタイムでも言われてるような閉塞感みたいなものは、先行きのなさみたいなものは、しっかり時代性としても出てくるんじゃないかなと。
生:あとはやっぱり、インターネットが出てきてSNSが登場して発達して、っていうのが俺らはより時間を浪費しているっていう意識を強めさせてるんじゃないかなって俺は思う。これってすごい言われてることではあるんだけど、昔って本当に狭い範囲でしか人々の繋がりはなくて、村社会みたいな感じで100人、多くても200人?まあ詳しくは分かんないけど、そういう直接的な繋がりしかなかった所、今はどこのやつか知らないし喋ったこともないけど、名前と顔は知ってて、でインスタ繋がってるみたいな。それで別に繋がってなくても、インスタ見ればこの人が何してて、同じ年齢でこんな子すごいことしてるのとか。自分のブランド立ち上げて服作ってる。音楽作っててめっちゃ人気だなとか。フォロワーめっちゃ多いじゃん。インフルエンサーしてんだ。とか昔は遠い存在としてテレビとかメディアとかの媒体でしか見なかったすごい奴らが、SNS一つで身近にすげー奴らがたくさん居るもんだなって可視化されちゃってるじゃん。でもそれに対して、この人達に比べて俺は何もしてねーなって。
でもビリー・アイリッシュと俺は同い年だけど、ビリーの目覚ましい活躍を見たり、音楽聴いて同い年でこんな詞書いて歌えるの?天才じゃんとかって思うけど、じゃあそれが焦燥感を覚えるのに繋がるかって言われたら別にそういうことじゃないよね。だって大スターで存在として遠すぎるから。逆にSNSにいる、存在としては身近だけど活躍している人達に焦燥感を覚える。
柊:でもそれって本来の姿じゃないし、虚像なのに自分達は踊らされてる感覚もあるし。
生:本当にそうだね。頭の中で踊らされてっていうのは分かるだけど、それでも結局その人の実態が掴めないからこそ、焦燥感を覚えるのに拍車をかけるのかなって。さっき、「On the Run」で訳も分からずティーンを駆け抜けているって言ったけど、今って小中学生?とかで携帯持ち始めて、それでSNS始めてまだティーンとして駆け抜ける段階なのに、同じ世代のすごい奴らをSNS越しに見て、勝手に焦燥感を覚えさせられる。自分は遅れてるなとか、無駄な時間を消費してるなって。その感覚が、時代が進むごとに速くなっているんじゃないかな。
柊:明らかに早熟化してるよね。
和氣:今生の話聞いてて思ったんだけど、ティーンの頃から情報化が進む中で、俺の周りだけかもしれないけど、焦燥感が加速し過ぎてニヒルに陥るとこまで行っちゃうやつがすごい多くて。実際に常にラリってるような友達もいたりして。エモ・ラップの台頭なんかは象徴的。10年代半ばから抵抗の音楽だったHip-Hopが解体されて、逃避的になって行った。それは疲弊の現れなのかなって俺は思った。だからエモ・ラッパーは、情報社会に疲弊してる10代、20代前半の奴らのカリスマになったんじゃないかな。だから「Time」を聴いたら説教臭く感じる若者も多いんじゃないかなって。
生:なるほどね。
和氣:それこそ俺らみたいに、NOISEで一発やったるべって言ったら、お前らうるさってそれこそノイズみたいに感じる同世代はいるんじゃないかな。
柊:それこそ今の話聞いて俺の思うこと繋がるんだけど、やっぱり疲弊感みたいなものの正体の一つとしては「Time」が73年に出てるっていうのもあって、73年っていわゆるX世代が結構生まれた年なわけじゃん。
生:俺らの父母が生まれたのとドンピシャ合うぐらいだね。
柊:それでやっぱ根本的にあるのは、やっぱX世代とかその上の世代に比べたら圧倒的にZ世代の方が俺らは思考はしてて、というか思考させられる状況には陥ってて、結構X世代の愚かさみたいなものから来るものに対するカウンターとしてあったMe too運動とか、Black Lives Matterが激化したのも、上のX世代への憤りみたいなところみたいなのもすごい強いから、 (Timeが)説教臭いって思うのも、俺らの親世代のお前らがやってたことってどうなんだよっていう。地球環境問題とかって声を上げてる、若い子いたじゃん。
生:グレタさんだっけ?
柊:そうその人。グレタみたいに、俺らの下の子達で環境がやばいって考えてる子たちはいっぱいいるし、俺らの同年代で環境問題に関心がある人達は絶対にX世代よりは多いわけで、そういう上の世代がやってきたことに対する憤りみたいなものを感じるっていうところから、説教臭さみたいに感じる部分はあるんじゃないんかな。
でも、それと同時に、「Time」で歌われてるような、周りが動いていくのに自分が動いてないっていうのは、そういう関心を持つ人たちが増えて、世界に対して前向きにアプローチしていく人たちが増えている中で、それに取り残されている自分っていうのもさらに、孤独感も増してるみたいな。 やっぱり出てく、やっていく人たちが出てく一方で、それに取り残された人はさらにその閉塞感に苛まれて、X世代への恨みも持ちつつ、自分たちの世代にも共感できずに置いてかれる人たちが、何もない1日を過ごして、時間だけが過ぎてくのを待ってく。
なんか、例えばその歌詞で出てくる、雨が降る、太陽が出てくっていうのは、やっぱ世の中では色々な出来事が起こってるっていうメタファーでもあって、その中で自分はただ1つ部屋の中にいる。例えば、日本も世界の情勢がどんどん変わって、グローバルサウスとかがどんどん出てきてとか、ロシア、中国が台頭してきてっていう中でも、(日本は)何もせずそこにいただけ。でも確実に自分の家の目の前で起きてる雨が降ってることだったりとか、太陽が昇ってることすらも、それを見てるだけの存在であったっていうのも 、なんかZ世代に限らず、日本人っていう感覚でもこの曲はやっぱり刺さってくるんじゃないかなと思う。
生:もう本当におっしゃる通りです。柊の言ってたZ世代は興味関心は以前より高くて同世代で活躍している人達がいてしかもSNSでそれが可視化されるようになった一方で、和氣が言ってたようにそういう人達に対して説教臭く感じてニヒルに陥って人もいるっている。なんていうんだろうね。逆行しているというか。
和氣:めっちゃ捻れてきてるよね。
柊:でもそれは、インターネットっていうものがさ、全てのものを民主化した、全部に広く平等にしちゃったことによる弊害だと思うんだよね。今までは、例えば成功してる人がいても、それは権威によるものだったり、家柄とか出生によるもので、成功してるって距離を置けたんだよね。逆にそれができなくなって、(インターネットで)民主化されたことによって、 自分たちは上がっていけないけど上がっていく人たちもいるっていうので、ニヒルに走っちゃう方向も出てくるし。
生:今でも昔と変わらず家柄とか権威で成功している人は勿論いると思うんだけど、SNSでそういう人々が以前より見えるようになったし、プラスで民主化されたことによってそういう人達だって一気に分からなくなった。違う世界の人だって距離を置けた人達とも今は置けなくなったから、等身大って思って比較してしまうっていうのはあるね。
和氣:取り残されていった人たちがエゴに苛まれてニヒルになってシニカルになるんだね。Z世代は揶揄されがちだけど、SDGsに対する関心が他のどの世代よりも高いっていうデータ見たことあるし。
柊:あとこの曲の、だらだらしてるっていうのは絶対にサマー・オブ・ラブ、ヒッピーの影響はあるよね。
和氣:それはそうだね。
柊:今の時代にはヒッピーはいられない。
生:けどヒッピーの影響がある「Time」が今の俺ら、Z世代にも刺さるっていうのはすごくない?それって逆にヒッピーの時代に戻ってきてるって事なのかもしれないよね。短絡的な、どんどん手軽なエンタメに晒されて自己を消費しているっていう事は、ヒッピーが反戦って掲げてるのに快楽に身を委ねてたみたいな。その当時ヒッピーを嫌ってる人達も少なからずいて、例えばヴェヴェッツ(The Velvetunder Ground)のドラマーが言ってた事なんだけど、ヒッピーは何が解決できるんだ。そしたら、ホームレスの人を支援したりとか行動に移せ的なことを。3
柊:今なんか聞いてて見えてきた事は、今のTik Tokとかを見て消費してるっていう感覚は、やっぱヒッピーにもしかしたら
生:めちゃくちゃ近いよね。
柊:目の前にある快楽に飛びつく感覚。でも、その上には反戦っていう大義名分を持ってくることによって、それを正当化できるみたいなところに俺らもあるかもしれないよね。SNSとかを見るっていうのも、情報を見るとか、世界の潮流に取り残されないようにするっていう名目のもと、SNSとか見てるけど、実際見てるのは家の中で。現実世界には実際にはいないところで。ただ家の中でSNSを見て、世界と繋がった気になれちゃう。
生:行動してる気にはなるよね。
柊:そう。だから、カリフォルニアでヒッピーがやってる時も、結局あいつら別にベトナムに行くわけじゃないし、ベトナムの戦地に行くための飛行場にいたわけでもないやつらが、あそこで大麻を吸うことで反戦の行動をしているかって言ったらそうじゃないし。確かにここが接続できるのすごいね。
生:短絡的、目の前の快楽に飛びつくって言うところでは完ぺきに接続できるよね。
和氣:でも俺らの世代ってヒッピーと比べて大義名分が希薄じゃん。情報社会を生きるので手一杯というか。だから、サマー・オブ・ラブみたいな華やかさがない。悲観的な風潮があるよね。
柊:うん。てか自己欺瞞だし、もう諦めてるとか諦観的になってるところがあって。でもそれはさっきも言った、もうこんなどうしようもない世界作ったのお前らじゃんっていう上の世代への憤りもあって、 しかも多分ヒッピーより情報は多いから、俺らは色んな情報に触れてるわけじゃん。俺らはこういうことがあってこうなってるとか、世界がどうなってるっていうのは知ってるからこそ、もうどうにもならないってニヒルに走る。
生:色々な事に晒されて知れちゃうからこそ、逆にもう無理じゃん。情報量に圧倒されて、やる事が多すぎる。時代の積み重ねの中でやる事が多すぎて一個一個処理したって無理だ。前の世代に対しての憤りもありながら、自分達の世代でも疲れていると。
柊:だし、なんか当時の「Time」は、先が見えない感覚で、終わりがいつか来るっていう感覚だったけど、多分その世代より俺らは、それこそ気候変動とかで地球が終わるのを知ってる。どう終わるかまで考えちゃってる所あるから、時間の方からこっちに迫ってきてる感覚を俺らの世代は持っているんじゃないかな。
生:でもその世代が見てた地球の終わりってまじで核戦争とかじゃないの。
柊:でもそれこそさ、その当時は核戦争が今より、今よりはあったわけじゃん。目の前にあったことだからこそ、こうやって「Time」って歌ったのかもしれないし。だから、 現実的な終わりかどうかは別として、その世代は核戦争で、今の俺らで言う気候変動とか、俺らも核戦争って問題とかはあるけど。どちらの世代も明確な、はっきりとした絶滅というものが見えてるのかも。
生:俺らの世代は環境問題とかあとは人種の分断とかそういった絶滅が見えてる。でもその当時は、核戦争という絶滅が見えてた。
柊:その中で、どちらの世代も短絡的な快楽に溺れていく。Z世代がベトナム戦争下のヒッピーと接続していくのは面白い観点かもしれない。
和氣:情報化の失敗について上がったけど、これはThe 1975の「Love It If We Made It」って曲で歌われてて、情報社会を生きるユースのアンセムだと思ってるんだよね。この曲って、つらつら情報化の弊害みたいなのを並べるんだけど、でも最後の最後に俺らが作りあげたんだから愛そうって。でもそれもやっぱ欺瞞じゃないけどさ、今のユースにあるのってそういう諦観みたいな強度だと思うんだよね。あとふと思ったけどケンドリック(Kendrick Lamar)の「Alright」とかもそうじゃないかな。歴史を通してブラック・コミュニティの人々が受けてきた事は凄惨でも、「Alright」大丈夫だぜって。二曲とも細かい所見れば違うかもしれないけど、なんか根底に流れるものは同じような気がするな。
柊:受け入れる。立ち向かおうってよりか。
和氣:そう。なんならもう愛しちゃおうみたいな。
柊:だし実際に俺らが作ってない問題が大半なわけで。でもそれらを請け負ってでも愛そうぜっていう部分もあるし。
和氣:俺らは受け入れて歩みを進めるしかない。Timeの歌詞の通り、ニヒルになってるだけでは淘汰されるだけだから。ケンドリックはAlrightで俺たちは大丈夫だってラップしたし、Mattyは何かを作り上げることは素晴らしいって歌ったんだと思う。
※これらの会話は1時間近くあったものを抜粋し、編集を加えたものです。
文:遠藤生
- 歌詞はGeniusから引用
https://genius.com/Pink-floyd-time-lyrics ↩︎ - 会話の中では「On the Run」の楽曲を詳しく説明できなかった為、ここで行いたい。まず、ここでは主人公の走る音がするが、ここで走り迷っている場所は空港である。それはこの楽曲で空港内のアナウンスが入っているところから分かる。しかし、空港というのはここでは将来の職業や進路の選択であったりをするために通う学校をメタファーであり、つまりほとんどを学生として過ごすティーンの時代というもの自体も空港に例えている。そして、空港にいるという事は勿論飛行機に乗って行く先がある訳だが、飛行機に乗る=ティーンが終わり自分の選択した将来に向かい、大人としての人生の「旅路」に就くという事だ。だが、空港というのは広大で、時間に余裕を持って行動しなければ迷い飛行機に乗れないように、主人公もティーン時代の苦悩、葛藤などもあり、「旅路」に就く前に迷っているのだろう。しかし、なんとか選択でき離陸する事はできたのだが、最後に爆発音がする。それは主人公の挫折であったり、ドロップアウトしたという事ではないのか。そして、次の楽曲の「Time」では挫折した主人公が故郷に帰り実家にいるというのに繋がっていくと筆者は考える。 ↩︎
- 2021年にApple TV plusで配信が開始された、「The Velvet Underground」の中でThe Velvet Undergroundのドラマー、モーリン・タッカーが以下のように述べている。
ラブ&ピースって何なの。現実に目を向けてよ。誰もが素晴らしいとか、平等に愛してるとか、撃たれずに世界平和を実現できたら理想的だけど銃を向けてる相手に花を渡しても説得できない。それなら、ホームレスの人を支援するとか、行動に移さないと。花を髪に挿して歩き回っててもダメ。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを視聴 – Apple TV (日本) アイコンとなった伝説のロックバンド、そのレガシーに迫るドキュメンタリー。彼らの目まぐるしい軌跡と時代に与えた衝撃を、貴重な tv.apple.com
↩︎