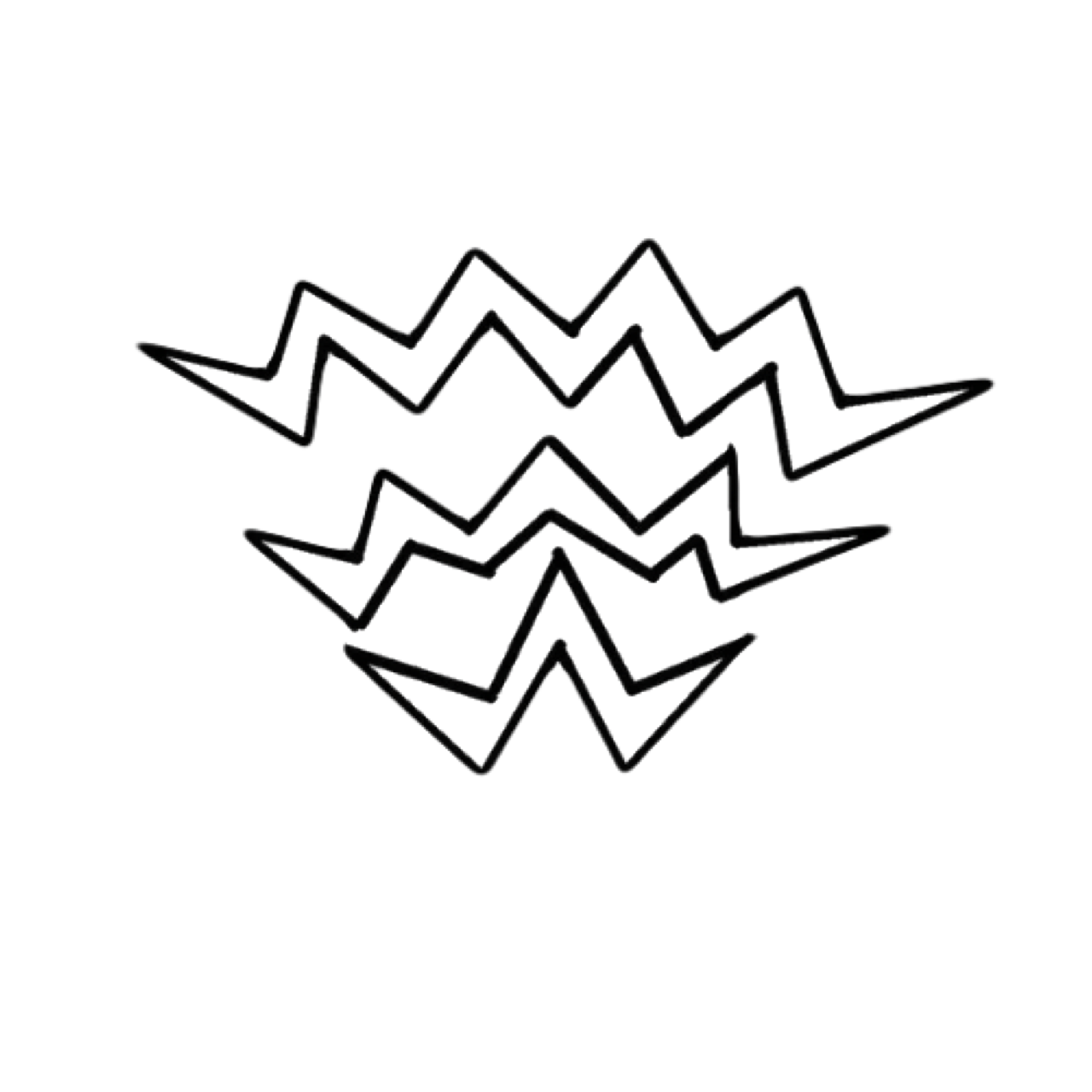偉大なるロックバンドHYUKOHとK-POP
先日2025年のフジロックフェスティバルのラインナップが発表された時、私はその中に多くの韓国アーティストの名前があることに心踊らされた。Blming Tiger、SLICA GEL、そして今回記事として取り上げるHYUKOH。多くの韓国またはアジア圏のミュージシャンが日本だけでなく世界の音楽シーンにおいて躍進を遂げる中、フジロックフェスティバルへの出演とバンドの活動10周年を記念して、ここではHYUKOHというバンドの偉大な功績と、彼らが韓国音楽へ与えた多大な影響を振り返りたい。
2025年現在、日本だけでなく世界中の多くの人が韓国の音楽と聞いて初めに思い浮かべるのはきっとK-POPだろう。BTSやBLACKPINKなどのグローバル市場での成功なども記憶に新しく、彼らに追いつけ追い越せの気持ちで日々新たなグループと、その楽曲やビデオが誕生するその瞬間を目の当たりにしている。しかし我々がそんなK-POPの動向を追っている間、その動向に大きな影響を及ぼしているのは韓国のインディシーンの音楽だ。そんな韓国のインディシーンを出自とし、K-POPとインディシーンが相互作用を生み出す中で多大な貢献をしたのがHYUKOHである。以下それについて書く。
HYUKOHという先達
HYUKOHの音楽性を紐解いていくに際して言及しなければならないのは、その影響元となる音楽がアメリカのものに限定されないということだ。Stevie WonderやRed Hot Chilli Pappersなどの音楽からの影響Vo.のOhhyukは以前から影響を受けた音楽としてThe Whitest Boy Aliveなどの名前を挙げている。このことからも分かるように、彼らのサウンドや楽曲アプローチには北欧やヨーロッパまたは南米ルーツの音楽が多大な影響を及ぼしている。そして彼らはその影を取り込んだ非常にハイレベルなバンドサウンドとして作品に昇華した。そんな彼らの作品はインディシーンや業界における堅実な信頼を得たのみならず、韓国の若者の声として迎えられた。こうした脱アメリカ的な音楽の要素がここまで歓迎されるような状況を作っていたのは、後続のアーティストに多大な影響を与えることになる。そしてそれはK-POPの業界においてもだ。その好例とも言えるのがNewJeans(ここで扱う作品はNewJeans期のものであるためこの呼称を採用させていただく)だろう。彼女らの作品のプロダクションには多くのインディシーンのミュージシャンが参加していることで知られている。250やFRNK、OOHYO、Cho Hyu-Ilなどさまざまな音楽性を持ったインディシーンのミュージシャンの参加の恩恵もあってか、NewJeansの楽曲には多種多様な国や文化圏の音楽の影響が随所に感じられ、それによりリスナーに新たなK-POPを提示することに成功した。これはK-POPシーンとインディシーンが手を取り合ったことによる化学反応でもあり、二つの音楽シーンが生み出した相互作用が花開いた瞬間でもあった。詳細は割愛するが、同じことが昨年リリースされたBTSのメンバーRMのソロアルバム「Right Place, Wrong Person」でも言えるだろう。
こういったことからもRMのアルバムやNewJeansのヨーロッパ的なアプローチの目新しさの根源には、すでに韓国インディーのシーンでHYUKOHを筆頭にさまざまなミュージシャンが行っていた手法に対する嗜好が、出来上がった基礎としてリスナーの中に潜在的に機能していたのではないだろうか。それ以前のK-POPが志向する海外マーケットはアメリカ的なものが多く、アメリカの音楽市場の動向に向けたような、ディーヴァ的に賑やかで派手な印象なもの(特にガールズグループでは)が多かった。それに対して彼らのようにヨーロッパ的な音を取り入れたサウンドやプロダクションが、皮肉にもアメリカ市場における最先端を作るのに作用したようにも思える。またそういった流れは、世界の脱極的な動向にも呼応していた。そしてそんな現象が日本よりさらにグローバルにカルチャーがクロスオーバーする、韓国の音楽シーンの中から起こったというのは必然的とも言えるだろう。
さらにそうしたHYUKOHのクリエイティブの先見性は、音楽面のみならずヴィジュアル面にも及んでいる。「Gondry」という楽曲では大胆にMichel Gondryの名前を楽曲名に用いながら、そのMVは彼の作品や岩井俊二の作品のオマージュになっている。ここでオマージュされているのは二人の監督の代表作である「Eternal Sunshine of the Spotless Mind」と「Love Letter」である。この2作品は今やY2Kリバイバルの機運や韓国での根強い人気のもとで、若い世代にとっては恋愛映画の傑作としての認知を確固たるものにしている。Y2Kリバイバルの中心にいるとも言えるNewJeansの作品のヴィジュアル面でもこういった作品からのオマージュが散見されるが、この点でもHYUKOHはいち早くその機運を作り出す土台としての役割を担っていたように思える。
N放世代、何を手放さない
70年代から90年代にかけての急速な経済発展により目まぐるしく変化していった韓国社会。しかし97年の経済危機以降、若者の失業率は大幅に上昇し、彼らは社会的弱者としてそこにいた。2010年代に入り若者が置かれている状況の改善が叫ばれ、政府や自治体による政策が行われたが状況は改善するばかりか悪化していった。若者の状況が悪化する中で恋愛、 結婚、出産の三つを放棄せざるを得ない若者世代を指す「3 放世代」という言葉が登場する。さらにそれに人間関係、マイホームを足した「5放世代」、さらに希望と夢を足して「7放世代」、そしてこのように手放すものが増え続けることを指した「N放世代」なる言葉までが生まれた。
韓国の若者に共有される社会や自身の現在と未来の行き詰まり。HYUKOHの音楽はそうした若者の感情を緻密に描いていたため多くの若者の支持を得ることになった。(ヴィジュアル面でも90年代後半から2000年代の作家の参照が見られるのは、当時世界に共有されていたディストピア的な世界観と彼らの世代が共有するN放世代的価値観がリンクするところからも納得がいく。)そして彼らがそうした韓国の現状を正しく描いたことは後の韓国のアーティストたちの作品にも大きく影響を与えているはずだ。
そんな韓国の若者に共有される何もかもを手放す価値観に強く共鳴するような楽曲を多く残すHYUKOHの作品だが、それだけにとどまらないのもまた彼らの凄さといえよう。2018年リリースのEP「24: How to find true love」で彼らは別れを告げようとする。それは韓国という地を離れ世界に大きく一歩を踏み出すことであり、過去の自分との決別することであり、しがらみや争いの絶えない地獄との別れでもある。しかし彼らはそれらに簡単に別れを告げられるわけでもない。それらを手放し自由を手にした時には何をしていいのかわからない不安がつきまとい、これから離れる地へ未来から懐しさを覚え、地獄にもある美しき愛を讃歌する。この複雑にもぶつかり合う感情に誠実に向き合った作品を残してきたことも忘れてはならない。手放してしまうこと、別れを告げてしまうことの方が良いのかもしれない。それでもなおしがらみに塗れ、不安に駆られながらも地獄を生きる全ての人に本当の愛の見つけ方を説く。今のわたしたちが手放してはならないのは、こんなにも見苦しく、こんなにも醜い我々と葛藤し続けることなのかもしれない。
同志たちよ
ここまで彼らの功績やディスコグラフィについて書いてきたが、彼らの最近の活動からも目を離してはいけない。彼らの最新のプロジェクトは台湾のバンドSunset Rollercoasterとの共作アルバム「AAA」だ。このプロジェクトについて一番特筆するべき点は、この二つのバンドの出身だろう。韓国と台湾という東アジアにおいて、常にアメリカや中国、ロシアという現代世界における巨大な国家の緩衝地帯に身をおいていた2カ国。その恐怖と混乱の中を歩いていた彼らが出したアルバムのタイトルが「All Access Area」の略称であるのならば、同じ東アジアに生きる私たちにとっても、決して他人事ではないはずだ。彼らが死した仲間たちの高い高い屍の山上から海へ飛び込み、生き残るための戦いの中で若き同志たちに永遠の慈悲を歌う時、日本にいる私たちは何をしているだろう。韓国と台湾という国に守られているといっても過言ではない国に住む我々日本人に足りないのは危機感と覚悟なのか。それは確かに幸せなことでもありそれを享受している自分がいることも理解している。しかし我々もきっと同志であるべきなのだ。この先に待ちゆく世界的混乱を共にする同志として歩いていく覚悟が必要なのだ。学ぶことか死ぬことかを迫られるような世界で、どこにも正解や真実が見つからない世界で、共に生きて死んで行く覚悟と慈悲を同時に持って。
彼らの音楽は日本のリスナーにこそ聴かれるべきであると思っている。それは簡単に言えば韓国という国で今まで起きたことの多くに、日本という国が関係しているからであり、韓国という国にこれから起こることの多くに、日本という国の未来は深く関係しているからだ。これは批評家ならではのアフォリズム的な締めの言葉なんかのつもりで書いているわけではない。そんな態度は彼らの作品に初めて触れ、多くの感動と興奮を覚えた中学生の時の私が許さないだろうし、彼らの今までの偉大すぎるまでの功績とこれから先の功績を前にすれば、この文章の中では語りきれなかった魅力や発見が無数にあることも確かだ。しかしこの文章を足がかりに、まだ見ぬ同志が彼らの音楽にアクセスしてくれることを切に願う。
文:田中柊