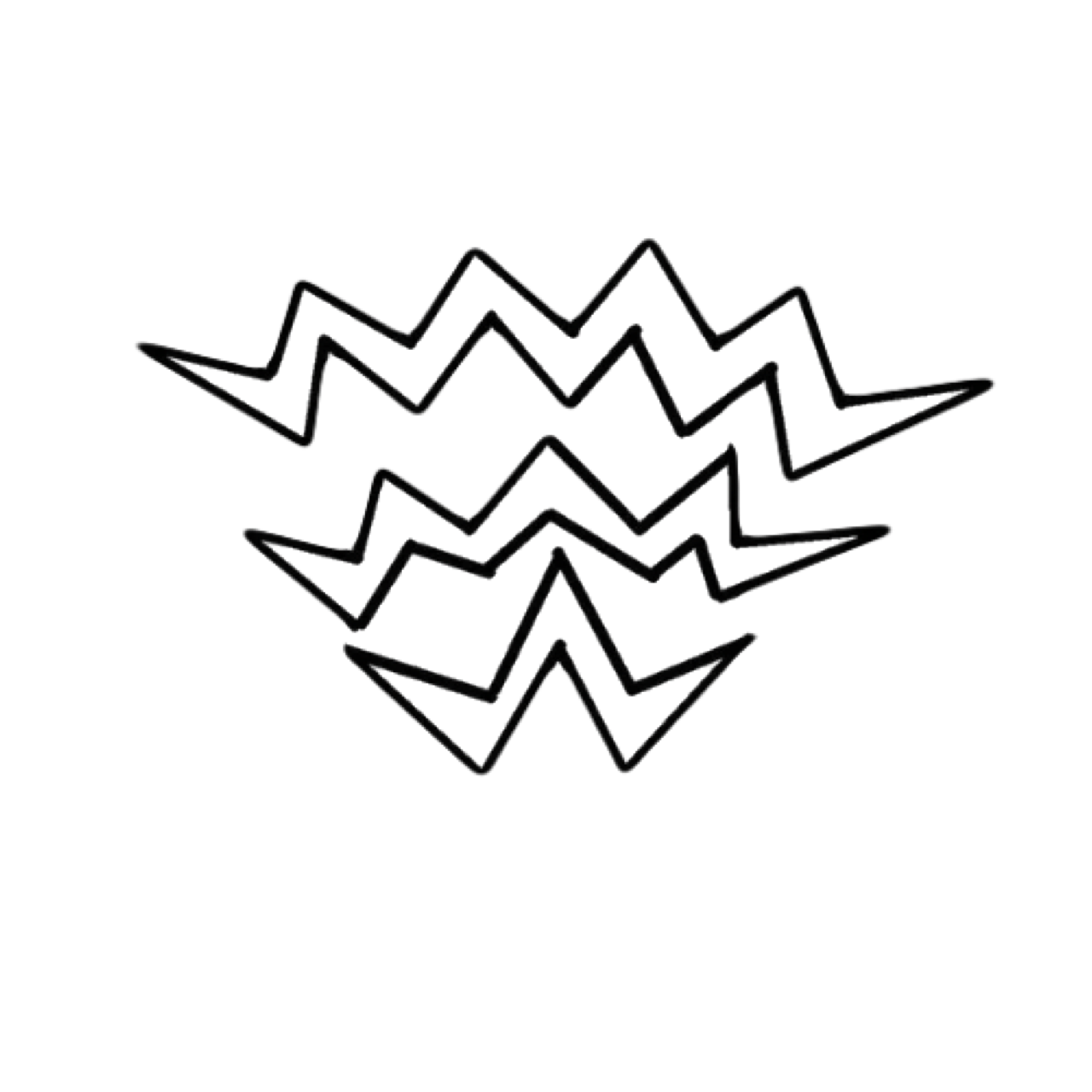BYORA 『jun!』 リリースワンマンライブ -運動の衝動は予測不能-
Shogo Mochizuki、Urban、MÜKÜの3人からなる3人組、BYORAの初のワンマンライブが、12月20日表参道WALL&WALLで開催された。
COMPUMAのDJsetが開演時間に近づいていくとともに、オーディエンスがフロアに集まり始める。彼らの友人や知人の数が多く占めてはいたが、そんな中でも確かに彼らの音楽と野心に心すらも踊らせる人の姿がなかったわけではない。
デビューアルバム『jun!』の一曲目のスキット『jun’s voice』が開演の時刻を指し、BYORAの3人がステージに立った。『abura』のイントロとともに3人の全身のエネルギーを一度も体に滞留させることなく空気中に放出するかのような瞬間的な感情の爆発を目撃する。しかし、そこには確実に冷静かつ狡猾な音楽的快楽に向けた営みがあったことも事実だ。
過去と現在との距離や時間すらも飛び越え、ジャンクヤードから掘り出した、無作為なサンプルやサウンドが後片づけなどは微塵も考えず、無作為に会場に広げられていく。

その後も『watermelon』などの楽曲ではシンセサイザーなどで音を重ね、ドローン感を増し、アルバムリリースライブにおいても、常に新しい面白いことに手を伸ばす、彼らの好奇心をのぞかせるパフォーマンスが続いていく。そして、ライブが進むにつれて、会場にも徐々にBYORAの空気感が染み込む。
Shogo
「俺らヒップホップ大好きだから。オルタナとか言われてるけど。」
公演も中盤に差し掛かり、オーディエンスの耳が慣れてきた時、突然セオリーを裏切るように語った彼らの言葉に嘘はないように思える。これ見よがしに名前をつけたがる今の音楽シーンのサディスティックな欲望すらも、この言葉の前では目を伏せてしまう。それほどまでに彼らの中には飼い慣らすことのできない猛々しい無意識の野生がステージ上でも見え隠れする。
その言葉と共に、オールドスクールなビートが熱気を帯びていき、ライブは別のプロットに突入していく。UrbanのストイックなラップとMÜKÜの抉りくるようなガサついた声、そしていやらしいほど無邪気なShogoのフロウ。3人のマイクリレーを前にオーディエンスは体の芯を叩かれたかのようにリズムを取る。そして、彼らのヒップホップへの敬意と、熱情に、体を揺らしながら、サッカー的なチャントをこだまさせていった。

その後も、アルバムのリードシングル『brat』では、サンプルの過剰供給と、点滅するライトの中で、三者三様の悦を見せながらの気を吐いたラップと共に、公演はフィナーレへと歩みを進めていった。
終わってみれば、今この時代にヌーヴェルヴァーグを自称する、言ってしまえば、厚顔無恥とも言えよう純粋な本能こそが、彼らを象徴スタイルになっていくだろう。
しかし、彼らが用いる手法は意識的で戦略的なアプローチではない。ゴダールが当時、作品の長さを短縮するという直感的な”必要”によってジャンプカットを生み出したように、BYORAもまた無意識的に自身の欲望に従った結果として、独特なサウンドコラージュや、文脈などから断片化されたような肉感のあるアプローチが生み出されている。だからこそ、彼らの楽曲はライブにおいてもオーディエンスとのやりとりではなく、彼ら自身との対話や壁当てとなり、彼らですら予想のできない展開や返球を見せる。その瞬間において、彼らの中にあるのは“ 楽しいかどうか” “おもろいかどうか”という直感的な欲望と、それに呼応するだけの運動能力だけだ。勝ち負けスポ根ゲームにおけるポジション争いになりかけたシーンにおいて、自らの欲望に忠実にあり続けるMCたちの姿を観るのは新鮮だ。オーディエンスの緩やかな反応をよそに、彼らは常に不敵とも言える笑顔を浮かべていた。それがなぜなのか私にはわからない。楽しさゆえか、全能感故か。そんな3人の姿を見るたびに恐ろしいとすら感じた。
目の前のオーディエンスに囚われず、大衆の視線やプレッシャーよりもさらに大きな自分の中の欲望と対峙することにより、遙か遠い先まで声を響かせようとする動物的な気概を感じざるを得ない。そんなパフォーマンスだった。ここまで疎外感を感じたライブも初めてだが、それに勝るだけの高揚が充満していた。その空気には自己すらも振り切るほどのスピットされた残置物が取り残されていた。
今後彼らは、自称する通り、シーンにおいてのヌーヴェルヴァーグ(新しい波)になり得るのかもしれない。それは、彼らの運動神経と突発的な欲望に引き出された、まだ見ぬ波。波は引いてまた押し寄せる。次に彼らに会った時、波はより大きなものになっていても不思議ではない。そして、それは私たちはもとい、彼らにもまだ知れぬものだからこそおもしろい。そんな不安と充実感の混じり合ったような空気が、会場から夜の街に駆け抜けていった。

文 :田中柊
写真 :渡邉隼