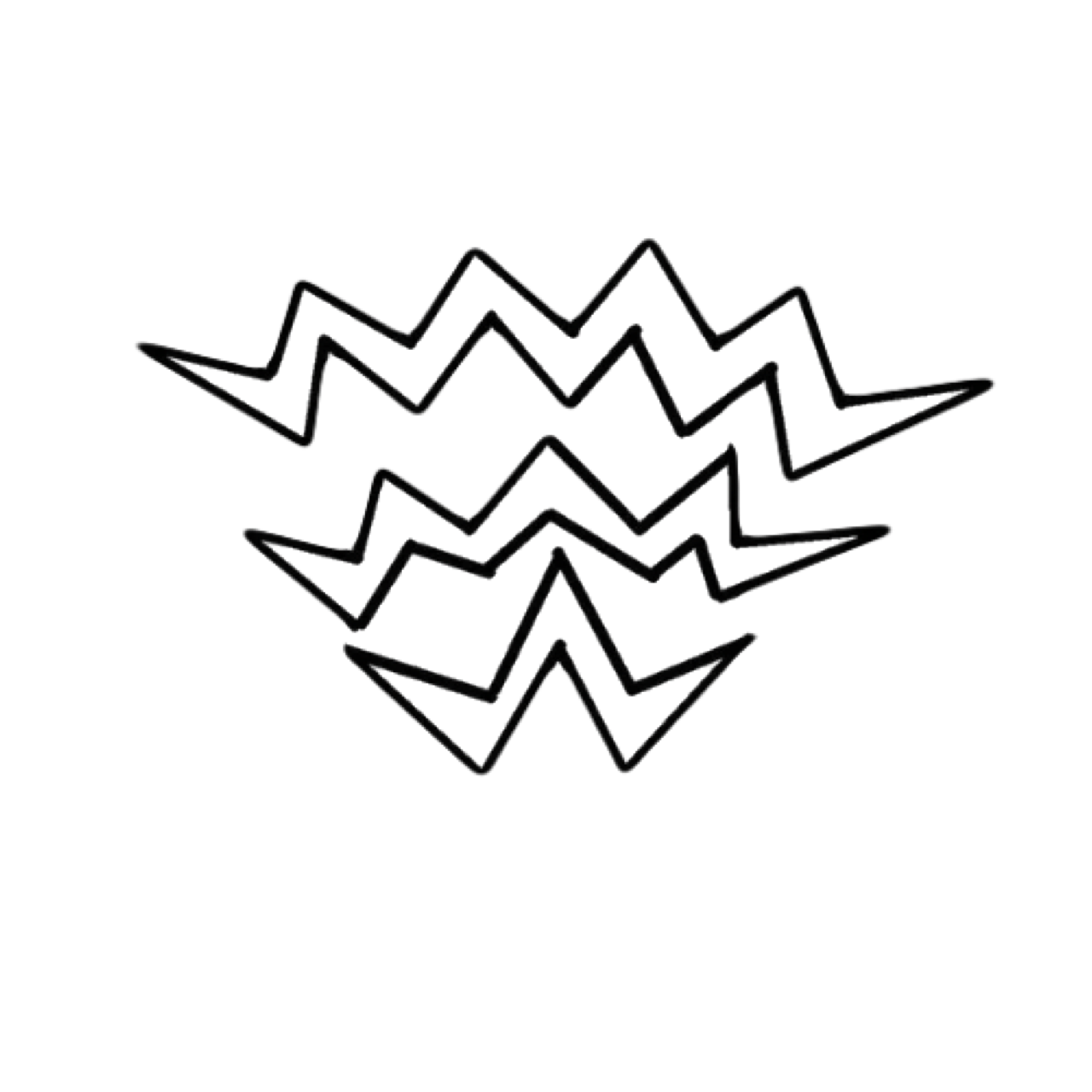宇多田ヒカル「BADモード」
〜ラブソングは誰のもの?〜
2022年初頭にリリースされた、宇多田ヒカルの通算8枚目のアルバム「BADモード」。その表題曲でもありアルバム冒頭の曲でもある、「BADモード」を発表からある程度の月日が経って改めて聴いてみると、この楽曲の強度に何度も打ちのめされるような感覚を覚える。人間活動と称される活動休止期間の前後で、彼女の作品には主題の変化が見られるが、それらの変化を超越した普遍的な彼女の在り方が、この一曲に滲み出ているからだろう。
絶えず変わりゆく社会や時代の潮流の上に身を置いてもなお、倒れず日本の音楽シーンのトップランナーとして走り続ける彼女の普遍的な在り方とはつまり、「揺らぎ」だろう。人間が物事のどちらにも完全な共感や帰属意識を見出せず、どこまでも孤独に、かつ身軽にその狭間で揺れ動き、彷徨い続ける姿としての揺らぎ(どちらにも属するというのとは似て非なるもの)。この曲には、彼女の持つ揺らぎそのものが、これ以上ないほど顕在化しており、「宇多田ヒカル」とは一体なんなのか、それについて今一度考える時間を我々リスナーに与えてくれる。
まずはじめにに触れなければならないのは、この曲のタイトルにも現れているナショナリティや言語の揺らぎだろう。前提として、「BADモード」なんていう言葉はどの国で辞書を引こうとも見当たらないだろう。ましてや、英語圏ではこのワードの意味を完全に捉えて表現する言葉はない。英語と日本語をはじめとする様々な言語精通している彼女が、あえてそれらをごちゃ混ぜにした和製英語ともいえる言葉をタイトルに用いていることは、アメリカと日本で生まれ育った彼女の複雑な出自と、それでいてその出自に縛られない彼女の身軽さと自由さを、端的に美しく捉えている。となると現在の彼女の生活拠点がロンドンであることも見過ごせない。彼女が自身の生活の身を置く場所としてロンドンを選んだ理由も彼女曰く、自分の友達や知り合いの助けがないところだから。自身を育てた地であるアメリカや日本も、彼女にとっては必ずしも帰るべき場所、帰属する場所として意識されることはない。常にどこにも属さず、出自を肩書きとすることもない。常に何かの間に浮かんでいるようなこの状態は、どこまでも孤独で苦しいものかもしれない。しかし、そういった状態でこそ、彼女はどこまでも軽やかに誰の手にも縛られない個としての彼女の姿を魅せる。だからこの揺らぎという部分にこそ、我々は宇多田ヒカルを見ることができるのではないだろうか。
出自のことで言えば、彼女の生みの親である藤圭子にもそれは関わってくる。言わずと知れた「演歌スター藤圭子の娘」。彼女がデビューしてすぐ、この事実が世間に知られてからは、このパブリックイメージは彼女と決して切り離せないものだったはずだ。そして、彼女の曲で登場する恋愛の対象が母であると思われるものがいくつもあるように、彼女にとっても、母というのは大切なモチーフでもある。そんな偉大な母の存在を背に、その”子”であることが付き纏い続けた人生で、その母を失い、更には人間活動期に自身も出産を経験し、母となった。そこには、子供としての自己と母としての自己、この狭間に揺らいだことからなのか、子供に対する好きというどこか歪で恋愛的な視点が向けられたり、はたまた恋人に対して、有り余るほどの母性の目が向けられる。こうした複数の主体の絡み合った立ち位置からか、この曲はリスナーが恋愛の歌にも親子の歌にも、どの様にも解釈して読み解くことができるスペースと遊びを生み出している。
それだけに止まらず彼女はマインド、または性においても揺らぎを見せる。曲の序盤で”君のこと絶対に守りたい”なんて決意をしたかと思えば、次の場面では”二度とあんな思いはしないと祈るしかないか”と自分の無力さのあまりを吐露する。自分が解決策になると言ったが、ジアゼパムを手渡し、さらには自分もともにそれを口にする。ポジティブとネガティブ、強気と弱気の間をも行き来するように自身の矛盾を繰り返していく。また、”私”や”僕”など一人称が安定しない様子などからも彼女のノンバイナリーな要素が顔を覗かせる。彼女の楽曲のリスナーがそのジェンダーやセクシャリティに関わらず、内容に共感して聞くことができるのにも合点がいく。幾度となく現れる複雑に絡み合った自己の揺らぎによってこそ、この楽曲の普遍性とポップスとしての強度は担保される。それでいて彼女自身は決してそれらのどれかをレプリゼントしたり声高に掲げることはしない。そう、彼女の中には自分をなんらかの集団や社会、コミュニティに帰属または接続させるためのアイデンティティという空想の旗が存在することはない。
”揺らぎ”こそが彼女の作品に多義的な意味と複数の多様な主体を含ませ、内省的で具体的な内容にも関わらず多くの人に共感や親近感を生む訴求力を生み出す。こうして”宇多田ヒカル”と名付けられたひとりの人間から生まれたいくつもの揺らぎは、この変わりゆく世界と自分とのなかで、幾千にも姿を変え万人を見つけ愛してくれているのだろう。しかし、そのどれにも彼女自身の帰属意識はないのかもしれない。つまり、私たちのことを歌ってくれる宇多田ヒカルなんてものは、本当の意味ではそこにいないのかもしれない。ましてや、あなたのための歌を歌う気なんてものは、微塵も持ち合わせていない。リスナーやファンダムといった存在に対して、心身ともに距離を取っているのだ。そんな態度こそ、混沌ともとれるアイデンティティポリティクスの風が吹き荒れた2010年代にぶつかり、内省性を強要されるコロナ禍を超え、SNSにおけるいいねという、実体のない共感に依存した価値判断を捨て、他者との中に介在する自己という存在を見つめたミュージシャンのあり方としては、どこまでも健康的でいて、自然な姿に思える。
文:田中柊