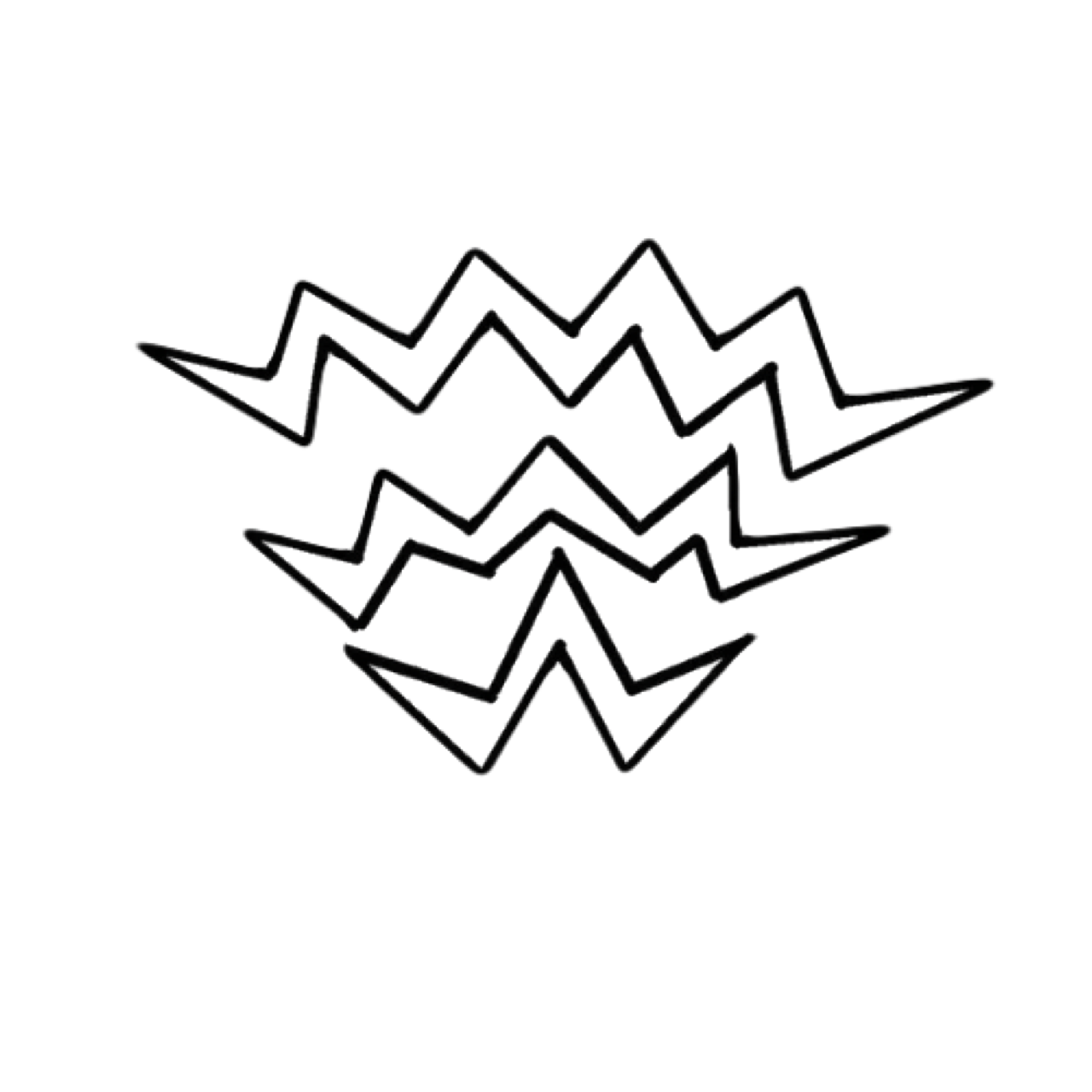From The Internet 〜インターネット以降の人間愛〜
「君はどこから来たのか」そう私たちが問われる時、それは科学的根拠に基づく歴史的事実だけが問題なのではないはずだ。”我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか” 属性によって正しさが測られる現代において、私たちをuniteするつもりだったアイデンティティという言葉は、帰属することのできるHomeであるはずの場所ではなくなり、隷属するためのHouseになってしまった。精査され規定される我々のアイデンティティとやらは、我々を縛り、働かせ、再生産に寄与させるための装置として機能する。HIPHOPが商業的な成功を着実に重ねていく過程で、そのアイコンとされた黒人男性(特にゲットーなどに暮らす)は商業的な成功のために、自らの苦しい環境や出自をリリックに乗せ、それが他人によりカリカチュアライズされ、そのイメージを再生産することに自ら寄与してしまったように。いつもは私たちが安堵できると感じる繋がりでさえ、時には苦しいほどに私たちを縛り付けるものとなる。
インターネットの登場は、そんな世界の在り方を変えただろうか。世界のあらゆる壁を取り払って透明性を向上させ、手段や情報の民主化を推し進め、高度な民主主義と自由の発展を生み出す。私はまだ生まれてすらいなかったが、きっとインターネットは誕生当時、このような期待を背負っていたのかもしれない。できることなら私もそんな期待を一瞬でも良いから持ちたかった。いまや私たちのプライベートな空間は気付かぬうちにどこかに持っていかれ、アルゴリズムを通じて企業により与えられる情報は、もはや神からの啓示かのように私たちの生活や感情の行き先を指し示す。(ヨルダン川への導きはそこで見つからないかもしれないが。)あるいは弱い人々が団結することによって起きる自由や高度な民主主義を恐れ、一人一人が自身のスマホとだけ向き合う状況を産むことによって、個人をより細分化し、団結することを防ぐ方向に向かってる。
また、インターネットやソーシャルメディアが私たちの生活のルーティーンに組み込まれてからは、プロセスする情報の波は、その高さも速さも日々加速度的に増している。それぞれの情報に載せられる感情的な反応を押し切ってまで、本質と向き合い磨耗して行く時間を持つことすらできぬうちに、次の波が打ち寄せる。気づいた時には自分は波に削り取られ、自分の姿かたちすらわからないものになってしまう。だからといってそんな状況に抗おうとしたところで、個人ましてや大衆が完全な理性や知識を追求することなど、到底できるはずがないことなどは自明だろう。今に始まったことではなく、私たちはいつの時代もどこまでも感情的で欲求的な存在である。さらにはそういった私たちの愚かな部分は、インターネットやソーシャルメディアを通じて、肥大化されているように写るかもしれない。しかし、私たちがすべきことはそうした感情や欲求を憂い、憎み、排除することではないと信じている。なぜならそれらを肯定した後は、アンチナタリズム以外のゴールを見つけることが私にはまだできていない(アンチナタリズムを暗鬱で否定的なものとは捉えていない、むしろ前向きとも捉えているが)から。我々がするべきなのはむしろ、そんな我々のどこまでも愚かで不完全な理性や知能のアマチュア性を担保したうえで、それらを駆使し、素晴らしくかつ愚かな集合知を生み出すために分業を行うパブリックスペースとして、インターネットを存在させることではないだろうか。そう、それはまさに蟻の群れが驚くべき集合知によって、人間でも難しいほど複雑で高度な構造の巣を作り上げるような営みだろう。しかしそこで私が悲観的になってしまうのは、私たちが思い描いていたインターネットの理想郷なんてものが、またはその片鱗すらもが本当に存在しうるのだろうかということだ。しかしその微かながらの希望を、私は一つの集団に見出したいからこんな文章を書いているのかもしれない。そう、それはどこからきたのかと聞かれて、「From the internet」と答えるような集団のことだ。
The Internetについては、まず彼らの音楽制作過程について語るべきだろう。彼らの初期の制作過程において、最も重要な役割を果たしたのがボーカルSydのスタジオである。彼女はOdd FutureやThe Internetの初期の制作のなかで、自宅のポータブルスタジオを使用していた。彼女が制作に用いたポータブルスタジオの存在は、彼らが世界に声をあげる手段を、彼らに与える大きなきっかけなった。これはひとえにテクノロジーの進展の表象とも言える出来事だろう。テクノロジーとは、それによって世界の在り方を変え、あらゆる壁を取り払ってしまうものなのだ。彼らの世界や音楽も、テクノロジーの進化によって与えられた手段により個人のベッドルームで作られ、Tumblrというソーシャルメディア(これも2010年代以降の手段の一つ)を通じて世界に投げ出された。誰もが自らの手段を持って、世界に自分の声や作品を訴えうる力を持ったということだ。時には、それが暴力的で反社会的と取られ、誰にも相手にされないようなものであったとしても。確かに声がそこにはあったということを世界に見せつけたのだ。まさにこれはインターネットによる高度な民主主義や自由主義の発展と重なるように思える。
さらにThe Internetがその素晴らしい力を発揮できるのは、メンバー一人一人の独立性と依存性との両方が担保された、そのバランス感覚に起因するものだろう。Steve LacyやSyd、Matthew Martin、Patrick Page Ⅱなどのメンバーはそれぞれソングライターやプロデューサーとして、または自身の創作活動でも活躍している。何度も言うことにはなるが、私たちが理想としていたポストインターネット世界の情景は、進展するテクノロジーによって民主化された個々人が、高度な民主主義を背に、どこまでも能動的に動ける世界だったはずだ。むろんThe Internetのメンバーたちもインタビューでも答えているように、彼らはそれぞれのソロプロジェクトをグループの離散とは捉えていない。むしろ彼らはそれらがグループの音楽性に良い作用をもたらすと信じて疑わない。個人が追求し、発展させた知性は結果的に全体やコミュニティの知性としても動き始める。そしてそれは決して専門性が必要なものではなく、どこまでもアマチュアネスに満ちた知性と共に歩む、それこそが社会であり世界であると言えるかもしれない。いうまでもなく世界がどう動くか、決定論的に全てを知る術を我々は持っていない。それでもそんなものたち同士で不完全な共同体として進んでいくのだ。そう言った意味でもThe Internetのバンドとして、またはメンバーの個人としての活動は、まさに我々が思い描いていたはずの、パブリックとプライベートを相互作用的に活用した、美しい集合知を実現させるための場所としてのインターネットの理想図に、限りなく近いのではないかといえる。
最後に、The Internetというバンドを語る上で、彼らの母体となったOdd Futureというクルーの存在と、彼らとThe Internetというバンドがどのような分離を果たしたのかについても言及しておこう。Odd Futureとは2008年ごろから活動を開始し、2015年に分解したクリエイティヴクルーである。Tyler, The Createrをリーダーに、Frank OceanやEarl Sweatshirtなど、現在の音楽シーンに多大な影響を与える面々がそのメンバーとして並ぶ。しかし彼らはただのラッパーの集まりではなく、プロデューサー、DJ、ビデオ・ディレクター、スケーター、シンガーなどで活躍するメンバーも中にはいる(そういった意味でもクリエイティヴクルーと呼ぶのが妥当と思われる)。このクルーを何かにカテゴライズすることの意味は果たしてあるかわからないが、あえてこのクルーを表す言葉があるとするならば、それは『雑多』または『嫌悪感』だろう。Tylerを中心とした彼らのアティチュードは「すべてのものをFuckする」ことだ。制度、政治、人種、性別、セクシャリティなどの、自分達の生活の前に浮かび上がるものすべてが、彼らにとってはFuckの対象になり得る。何より、それらが生まれる”世界”そのものこそが、彼らにとって最もFuckするべき対象なのかもしれない。しかし彼らの世界に対する眼差しは決して厭世的とは言い難い。むしろ多くの人よりもずっと野心的に、挑戦的に誰かの感情をかき乱していた。そんな彼らの姿に共感したリスナーや同業者の数は日毎に増していき、今では彼らは2010年代以降のアメリカないし、世界中のポップカルチャーに大きな影響を与えた存在とされるにまで至った。
しかし、そういったクルーのアティチュードが、そのままThe Internetに引き継がれているとは思えない。彼らはそれよりも、もっとパーソナルで性愛的な世界(楽曲やそれに付随した作品)を持っているように思える。そうそれはつまり、どこまでも肉欲的で、わたしたちの生きる現代のソーシャル世界では、一見理性とかけ離れていると思われているような世界だ。しかし彼らの世界は世間からの目などに左右され得ない。そう、彼らはそういった欲望こそを肯定し最も人間的なものとして映し出していくのだ。さらにそれらは、ただ単に耽美的な美の形式や、一種の趣向として肯定されているなんてものではなく、現代の価値体系そのものを反転させ、新たな価値観によって肯定するにまで至っている。人間の欲求的な部分にこそ理性を見出し、自らの不完全性にこそ美しさを見出そうとする。人間の中にある、理性と欲望という二つの要素を対立関係から解放し、新たな価値体系の上で肯定するということをやってみせたのだ。つまり彼らは、Odd Futureがやったのとは違う形で、しかし文字通り世界のすべてをFuck(性交)することに成功した。そうすることによって世界の全てを愛したのだ(これによりアティチュード的にも意味的にも両グループの分離が行われたとも言える)。その愛は時には醜悪な世界の現状や憂うべき未来にも向けられるのかもしれない。人はそれを破綻しているなどと非難するだろう。しかしそんな愚かさすらも親密な愛にすることのできる生物が、人間だと彼らは気づかせてくれるのだ。
ふと今から数年前を思い出してみる。誰かと一定以上の物理的距離をとることを強要されながらも、心理的あるいは精神的な距離は、0どころか内部まで入り込まれるような、歪な季節を越えて私たちはここまで来た。それでもなお、毎日のニュース番組やソーシャルメディアの中では、大衆の愚かさと醜さを鮮明に目の当たりにしなくてはならないことに変わりはない。しかし、その醜さをも愛したいと思う。それはきっと、どこから来たかもわからない、何者かもわからない、そんな誰かを誰かが強く抱きしめていく、そんな未来を望むような醜さこそを愛する(FUCKする)ことであり、それをしてくれるのがThe Internetだと私は信じている。
文:田中柊