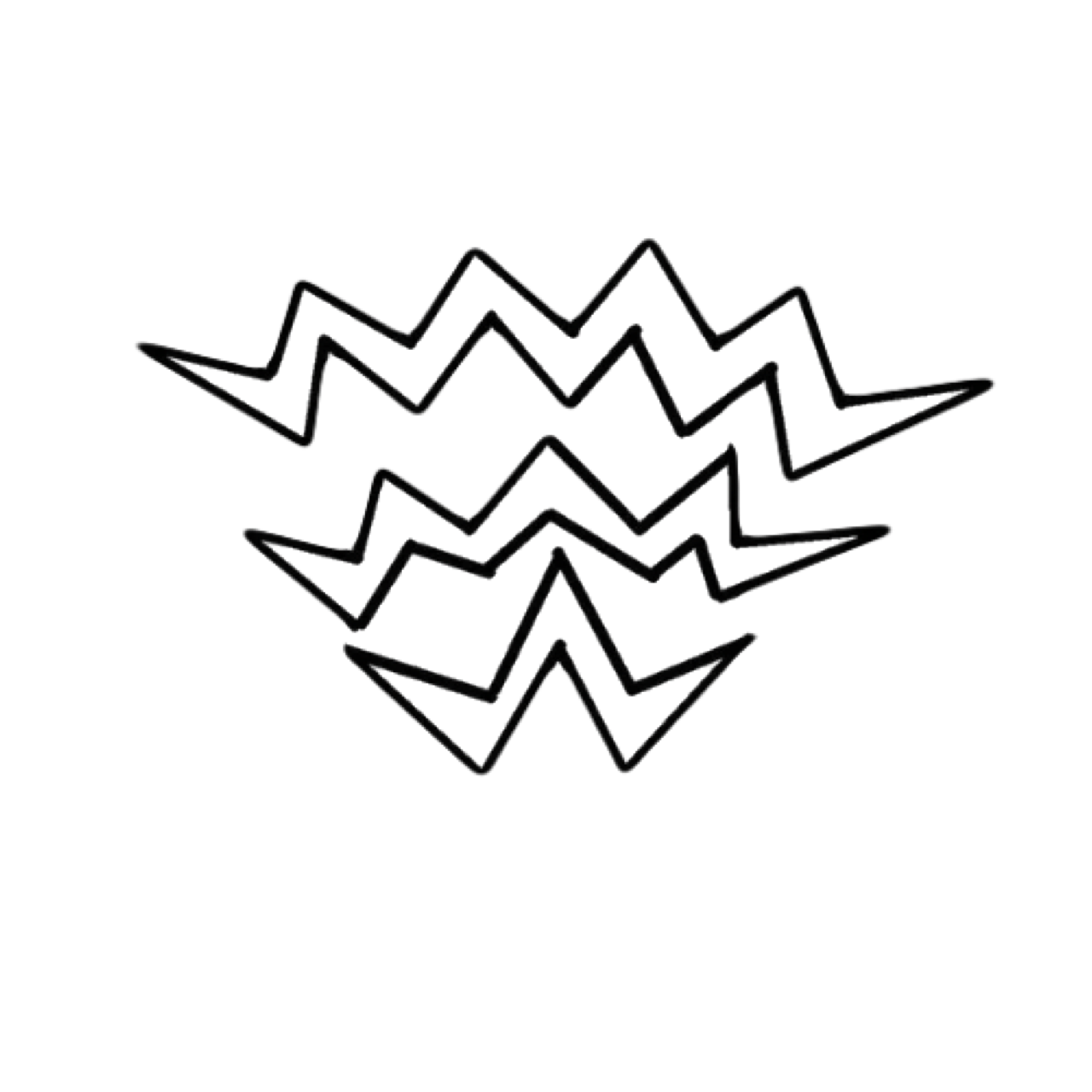千葉雄喜 『STAR』 〜今稼ぎどき、今が〜
千葉雄喜の『STAR』というアルバムを前にして、私は今書きたくてこの文章を書いている。瞬発力と運動神経だけでこの文章を書く。やりたいこと以外のすべてを置き去りにして書く。今が稼ぎ時だから。千葉雄喜についてわかんないけどわかるなんかを殴り書きする。1秒の中にのめり込んで書く。今が稼ぎどきだから。説明に割く時間は1秒たりともない。本題に入ろう。
また無に帰る
彼の口から突然発された2020年の引退宣言のあと、アルバム『worst』にて、祖母に向けた一通の手紙を最期に、KOHHは音楽の世界から身を引いた。彼はその楽曲の最後を本名である千葉雄喜の名前で閉じた。そんなマルセル・デュシャンからの影響が色濃く見えるコンセプチュアルなパッケージングで現れたKOHHによって、それまでの日本語ラップ界に蓄積されていた、スキルや知識、文明は無に帰った。寒気がするほどの肉体的なフローの洪水の上に、刹那的で極端に平易な言葉が浮遊するKOHHのラップ。正解が固定化されたように、完成されたフローと緻密なリリックを用いたそれ以前のラップゲームを前にして、100点満点の採点方法ではなく0点のままで正解になるような新たな回答を用意した。
しかしKOHHが登場した以降の日本語ラップは、彼の0点のラップすらも文明として、知識として蓄える事をやめなかった。KOHHに影響を受けたラッパーも無数に現れ、また直接的な影響を受けずとも、日本語のラップの実践という面において、彼の登場により拡張された日本語のフローと譜割りの自由度の恩恵を受けたラッパーの数は数え切れないだろう。こうして彼の手によってそれまでの歴史が一時的に無に帰ったことで、KOHH以前とKOHH以後に分けられるようになった日本語ラップの新たな歴史は、KOHHという地の上に道を整備し、また新たな文明を作っていった。しかし千葉雄喜としての彼の帰還は、KOHHとKOHH以降の日本語ラップによって作られた文明の蓄積をもまた無に帰してしまう。あそこまで身体と密接な距離を持っていたKOHHですら、千葉雄喜の前ではSt. ChromaなのでありTyler Okonmaではない。つまりKOHHとはペルソナに過ぎず、それを脱ぎ捨てた姿が千葉雄喜なのだ(KOHHという名前を無くなった父からとっていることからも)。多くのラッパーがKOHHという広大な大地の上でラップを吐き続ける最中、突如彼はその大地すらも無に帰してしまった。KOHHの中に我々が見つけていた肉体も、千葉雄喜や318がラップやアートを記述するために用いた機械的なペルソナであったに過ぎず、終わりが来るのは必然だったのだろう。そしてまた新たに千葉雄喜という肉体を我々は見つけたわけだが、この発見にもすぐに終わりが来るかもしれない。しかしこの緊張状態こそ我々がポップカルチャーに胸を躍らせることができる理由なのかもしれないのだ。ここまでのことからもアルバム『STAR』の直前にリリースされたシングル『誰だ』のなかで”俺は誰だ?”と彼が問うのは、自分が千葉雄喜であり、KOHHを脱ぎ捨てたありのままの姿ですら、STARであるということの証明として見ることができる。
過ぎ去る今
アルバム『STAR』は昨年12月12日になんの前触れもなく突如リリースされた。同時に武道館でのライブも発表され、目まぐるしい彼の活動を追いかけることに我々が必死になっている中、まだ11枚アルバムのリリースが控えているという発言があった。常に新しい楽曲の制作に取り掛かり、その中で特定のテーマでまとめられる作品をアルバムというパッケージングで届ける。その一枚目となる今作はSTARである千葉雄喜の生きる世界が鮮明に記されている。
『STAR』というアルバムには”今”が詰め込まれ、その中心にある千葉雄喜という星が燦然と輝く姿を我々は目撃する。しかし我々が今目撃しているその姿すらも、過去に彼が放った輝きが今ようやっと我々のもとに届いているに過ぎず、その輝きが彼の今の姿とは限らない。1秒前の過去を脱ぎ捨て、常に新たな今を彼は生き続けているからだ。その刹那的な煌めきの残像すらもが我々を驚かせ続ける。その輝く星と我々との距離はどのくらい遠いだろうか。その無謀とも思える測量に我々が勤しむ間にも、彼は地球7.5周分ほど先の世界の今を記述しているのかもしれない。我々が見つめる今ですら彼には過ぎ去った過去として写るのかもしれない。これがSTARを追うものに与えられた宿命とも呼ぶべき摂理なのか。これからの1年間を通して、我々は絶えず千葉雄喜というSTARに振り回され気を引かれていくのだろう。そんな我々の試みも意に介さず、ありのままの1秒を刻む彼の姿こそが輝いて見えるのだから。
他者への同調
目に映る現実をそのままラップする。それはもはやカメラにすらできない芸当であろう。彼は目に映ること、自身の身に起きることをラップする。たったそれだけのことのはずなのに誰にもできないことだ。しかしそれができるということによって彼がSTARであることを疑いの余地のないものにする。しかしそのラップのリリックに目を向けてみると、リスナーが同調できる(または自己を投影できる)部分など一つもないように思える。MeganとMTVアワードに出ることはないし、アメリカ大使館にお呼ばれすることもない、知らない女の子からハート絵文字やDMが無数に送られることもないだろう。こうしてただ一人の人間の目が捉えた写実的な事実そのものが超現実的に映るその時、ある種のお伽話のようなフィクショナルな空間が生み出される。誰にでもわかる言葉で誰も知らない、誰も経験したことのない世界のありのままを語る。しかしそれは現実に存在する世界のことである。そんなSTARが生きる世界に、同じく生きている我々もそこにいるはずなのだ。よって一見同調することができないリリックが連続する彼のラップだが、このフィクショナルな余白の部分にリスナーが居住するスペースが生まれる。そのため来たる武道館公演でも、パンパンなフロアに集まった大衆が、彼の楽曲のリリックを合唱する光景はいとも容易く目に浮かぶ。リスナーは千葉雄喜という他者が並べる平易で残酷なまでに写実的な言葉の中に、ある種のフィクショナルな空間を見出し、そこに入り込むことによって彼の言葉に同調することができるようになるのだ。
ここまで千葉雄喜の『STAR』というアルバムを前にして、書きたくてこの文章を書いてきた。しかし瞬発力と運動神経だけで書くことはできなかったかもしれない。無駄な時間は1秒どころか2日くらいあったろう。だがしかし私がSTARではないと気付かされようとも、私はまだこの言葉が嘘偽りないものだと言える。イマカセギドキ!イマガ!
文:田中柊