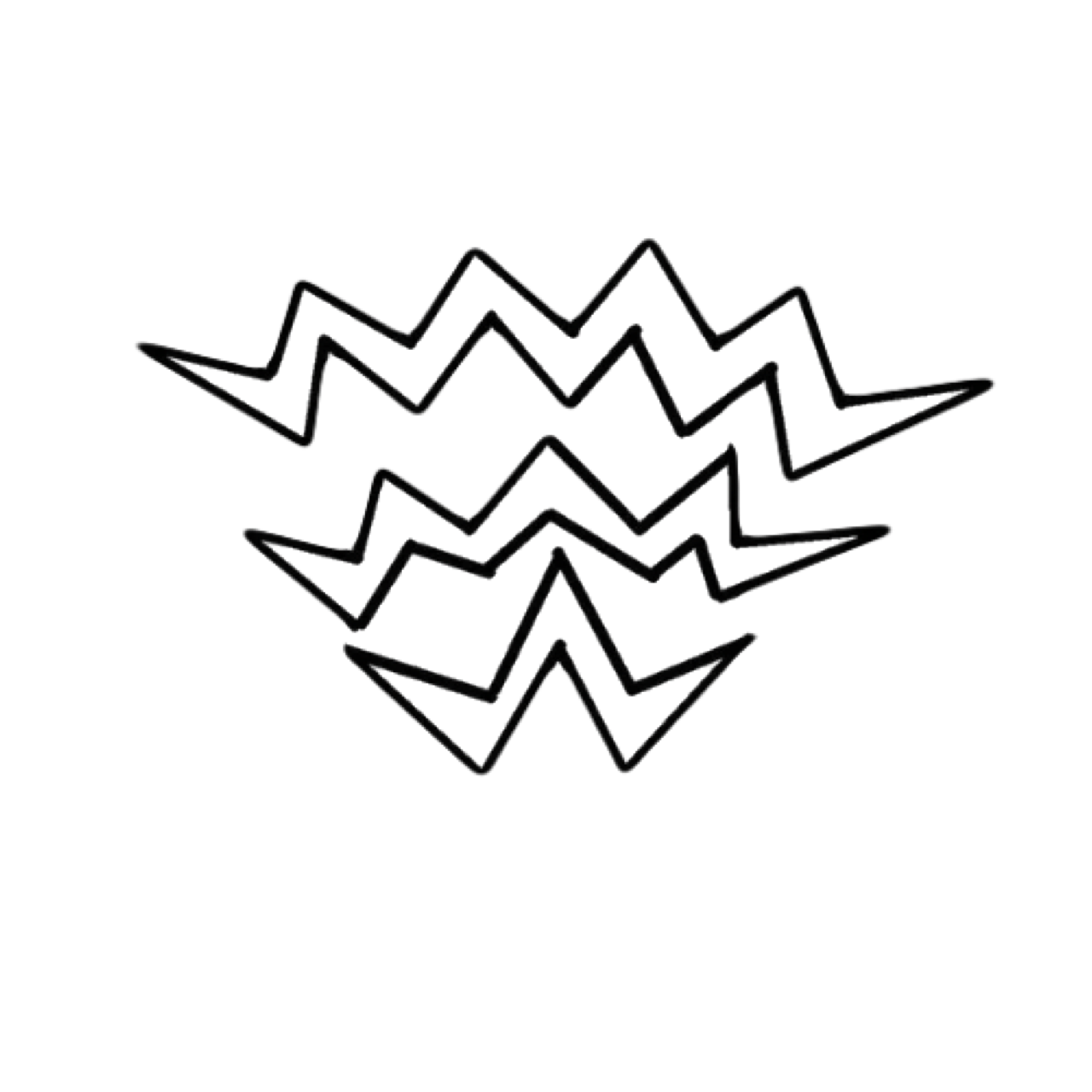リアルはリアルを超えてフィクショナル
あなたは海を見た時、その光景をラッセンの絵のようだと思ったことはあるだろうか。そんな経験はあるわけない、と思う人が大半だろう。しかし、本当にそうだと言い切れるだろうか。言い切れたとして、それはいつまで続くだろうか。この文章を読み終わる頃にあなたはそう言い切る自信をなくしているかもしれない。そして気づいた時には海を見てラッセンの絵と区別がつかなくなるなんてことが、もうすでにあなたの中には起きているかもしれない。では始めてみよう。
ラッセンの描くリアル?
クリスチャン・リース・ラッセンはアメリカの画家であり、海中世界とそこに棲むイルカやシャチといった海洋生物を描いた、マリンアートと呼ばれる作風で知られる。彼の作品はバブル期の日本において版画作品等を中心に人気を博し、今でも大衆的な作家として広く認知されている。
彼の作品は、彼の育ったハワイの海の美しさをサーファーだった経験をもとに描き出され、写実的ではなくドリーミーで幻想的な雰囲気を持った作品と言えるだろうが、世間一般が持つラッセンの絵に対するイメージもそうだろうか。むしろ、『一目見て何が描かれているかわかる。』という感想を持つ人も多いだろう。それゆえにかバブル期の日本では、芸術界におけるその批評的価値を置き去りにするかのようなスピードと規模をもって大衆に広まり、インテリアアートなどとも称されるまでになったのかもしれない。しかし、ここではそれらの現象やラッセンの絵そのものについて良い悪いなどと述べるつもりは毛頭ない。それよりもむしろ、ラッセンの絵に描かれているものを人が受容する瞬間にいったい何が起こっているのかを考えたい。
ラッセンの描いた海の絵は到底現実世界の海の姿とは程遠い。しかし、この絵を見て人々は現実の海を想起することがある。その時には画面の中に描かれる海らしきものが、現実の海の本来の姿として想起される場合と、この世のどこかに存在するかもしれない美しい海として創り出される場合とがある。前者の場合では、脚色や編集によって現実を改変する行為が行われ、後者の場合においては、完全なフィクショナルないし、リアルとフィクショナルの境目が曖昧になったような空間が創り出される。そのどちらにも共通するのがフィクションに触れることによってこそ、現実と自分とが自分の中で見つめ合うことができていると言う点だろう。つまりこの絵を見ているとき、多くの人の中では虚構に触れることによって現実が改変され、改変されたその何かを媒介として始めて現実が受け入れているのだ。Dos Monosの荘子itのいう、「人はアンリアルを通してリアルをリアライズするのだ。」ということだ。つまり、我々がリアルを受容するときには、フィクションを通してしかそれらを受容することはできないと言うことだ。いわば写実的でないのはラッセンの絵ではなく、むしろ私たちの眼差しと受容なのである。そうしたエラーとも呼べる現象を反復していく中で、人は何がリアルで何がフィクションなのかを見失っている。しかし、それによってこそリアルを凌駕するほどリアルなフィクションを描き得て、フィクションを超えたフィクショナルなリアルを発見することができるのだ。
BeRealに映るリアル
より若い世代の一番身近なところでこうした現象が起きているのが、ソーシャル上、特にBerealの中でだろう。ひとたび通知音が鳴ると、大勢が周りを見回して、携帯を手に写真を撮る。現代の大学の教室では日常茶飯事の出来事だ。また、1人で家にいる時にも、友達や知人があげた”リアル”な姿を目にし、彼らや彼女らの人物像を解像する。この行為が行われるとき、人の中には何が起こっているのだろう。そこで起きているのはリアルと銘打たれた虚構を媒介として、現実をフィクショナルな連続したイメージへと改変する営みである。切り取られた2枚の写真からなる投稿の中に映るのは現実などではなく、現実をフィクショナルに脚色し、拡大したイメージなのだ。お酒を飲んでいる姿を毎日あげたからといって、四六時中お酒を飲んでいるわけではない。おしゃれなカフェでの一幕を切り取っただけでも優雅な生活を作り出すことも容易い。しかし、そこに映るフィクションも現実を改変していく。そう、フィクションによって現実は新たな意味を持ったイメージの連続として立ち上がってくる。そうしてリアルと銘打たれたフィクションは、リアルを超えたリアルとして我々に受容されるのだ。そう、絵画という世界以外でもこうした営みは常に私たちの無意識のうちで行われているのではないだろうか。
このように、私たちは私たち自身が思っているよりもずっと都合の良いように世界を捉えている。見たものや聞いたものをそのまま受け取るのではない。自分の受け取りたいように改変して捉えているだけなのだ。いわばメタではなくベタで捉えているのだ。現在では主観的であるということが忌避されることも多いが、まず客観などははなから存在してない。今も昔もこれからも、私たちは皆ベタに生きているのだ。神を創り、神に創られたかと思えば、科学を説明し、科学に説明させたりしてきたじゃないか。だがしかし、それが悪いことなどでは決してない。むしろ、それでこそ人間が人間であるわけがあるというものだ。足音が聞こえてきているAI主導のホワイト社会を生きていく、この先の私たち人間にできることといえば、せいぜいミスをすることと、エラーを起こすことくらいになるだろう。だが、奴らには決してできないそのエラーこそ、そんな世界においても私たち人間が生きる意味となる。そう”エラーしながら正解する”。そんな一見馬鹿げた飛躍の体験を積み重ねることで人間は人間として生き得る。そんなメタとベタの境が壊れ行く中を生きているのだから、あなたの目に映る現実の海もラッセンの絵の中のものと差異ないものになっていると言って差し支えないのではなかろうか。
文: 田中柊