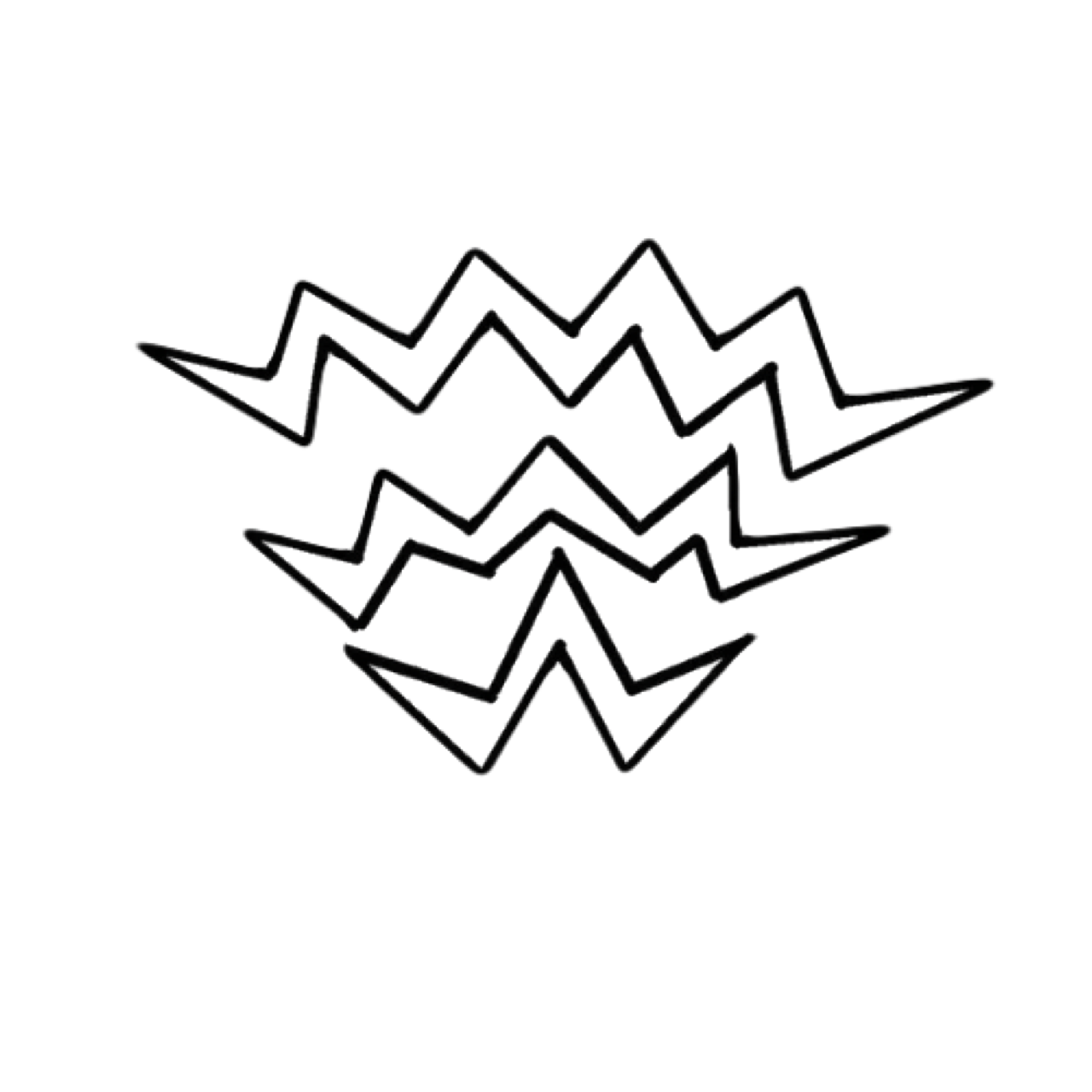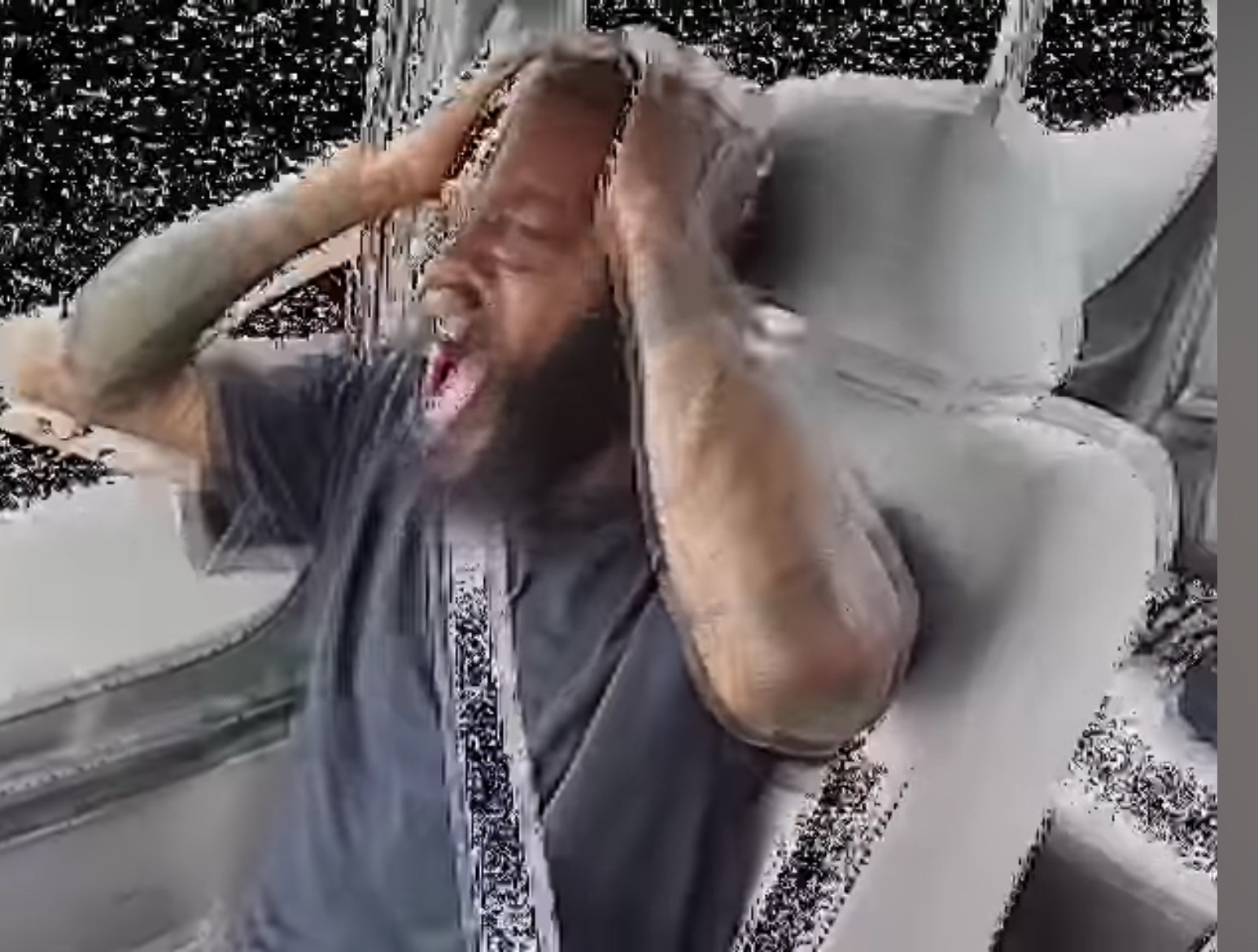
Death Gripsはなぜこんなにも「いる」のか?
これは評論ではない。Death Gripsに撃たれた身体の記録だ。
音楽とは、秩序によって立っている。あらゆる記号の連鎖が快楽や感動を生み出す装置として機能している。しかし、Death Gripsはその鎖を引きちぎる。ビット化され、相対化された、あくまでデジタルデータの断片を重ね合わせていく。そして快楽の裂けめから、肉片が飛び出してくる。それは、あらゆるコードを脱ぎ捨てた、いま、ここにある肉体の震えだ。さらに、Rideのリリックは広義の文法を持たない。意味不明なスラングやノイズに歪曲され、機能不全に陥った意味は腐臭を放ち、Rideの燃えたぎるような肉体が発露する。瓦解した言語の中から産声を上げるのは、喉、肺、熱、湿り、呼気、体温、それはつまり言語になる以前の、肉が軋む音である。そうして意味の亡骸はビートに堆積する。それは、意味や感情に奉仕するための音ではない。断片は調和を拒み、秩序は崩れながら、なお重なり続ける。咆哮と無数のノイズが、形さえ与えられぬまま堆積していくのだ。だが、その崩壊のなかでこそ、音楽はむしろ剥き出しの肉体性として立ち上がる。耳はあらためて聴くという行為の肉体性にさらされるのだ。Death Gripsは音楽に潜在する肉体性を引っこ抜き、それを鋭利な針のようにして、リスナーの耳に突き刺すのだ。
またMVにおけるMC Rideのヴィジュアルは暗く、粗く、匿名的だ。彼は、アイコンとしての「ラッパー」というコードを脱ぎ捨て、 身体をただの媒体(ノイズを出力する端末)として提示する。彼の自己同一性や身体は伝統的な人間のコードから引きちぎられ、デジタル信号として再構築されているのだ。彼らは、初期から見せないこと、語らないことを徹底している。だが、それは沈黙ではなく、激烈な拒絶である。2013年、彼らはLollapaloozaの公式アフターショーを突如バックれた。会場にはファンが書いた遺書のスクリーンショットが投影され、演奏の代わりに録音されたループが流された。虚無と期待の狭間で宙吊りになった観客の欲望はやがて苛立ちへと変わり、ドラムセットは破壊された。このような暴動が作品の一部と化すような構造において、Rideは物理的にはそこにいない。しかし、観客の怒り、動揺、反応の中にRideの像が立ち上がる。さらに同年、バンドはアルバム『No Love Deep Web』をレーベルの意向を無視し、無料でネット公開した。ジャケットには露骨な男性器の画像が使用され、レーベルとの契約は事実上破棄される。ここで彼らは産業構造における流通からも逃走した。Death Gripsにおいて不在はただのキャンセルではない。それは露出に対する批評であり、更に興味深いのは、かえって不快なまでの存在感を獲得しているという点である。いないのに、いる。肖像の崩壊によって、彼はより暴力的に知覚される存在となるのだ。彼が拒絶し、肖像を引き裂き、意味から逃走するほどに、私たちはその輪郭を指でなぞろうとしてしまう。Death Gripsはグリッチやノイズに引き裂かれてもなお、のた打ち回っている。
Death Gripsは、崩壊しているのに、不気味なほどそこにいる。