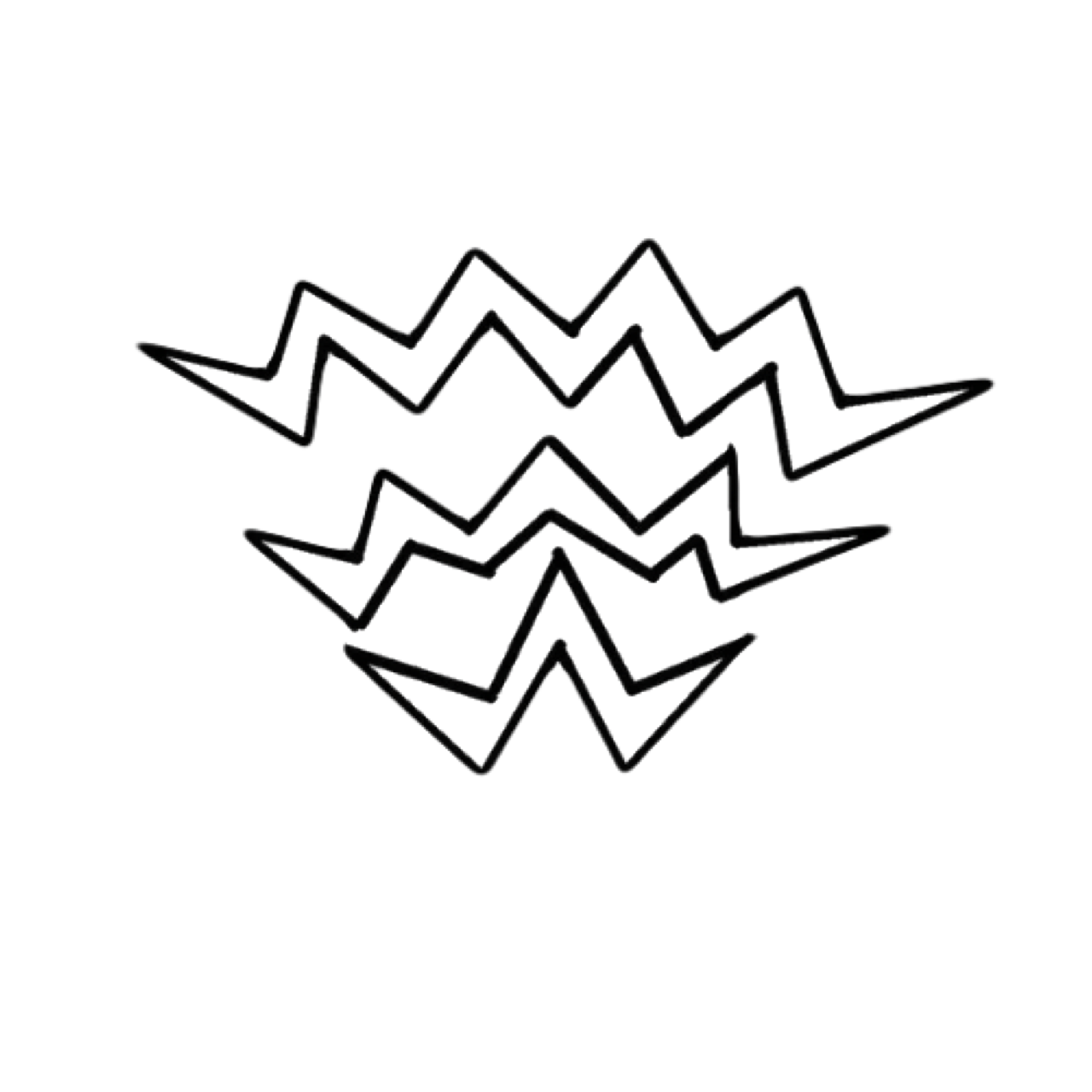ルカ・グァダニーノ最新作「Queer」で描かれた不真面目さ
「I’m not queer.」「I’m disembodied」
私がこの作品を観に映画館に足を運んだのも、観終わった後にこの文章を書いているのも全てこれらの言葉が理由だろう。ルカ・グァダニーノ監督の最新作「Queer」で描かれる不真面目さについて生真面目に書いてみよう。
どこかわざとらしくて嘘くさいメキシコシティの街並みのセットの中、咽返す暑さをも美しい物語の契機に変えてしまうかのような、しなやかでいながらもくたびれたジョナサンによるスタイリングを目にしたとき、図らずも口元が綻びていることに私は気がついた。いや、それよりもずっと前のシーンで私の文章にも似て、集中や整然とは程遠いような無数のカメラの切り替えと、不気味なカメラの位置、そして何よりもこの映画の中ではシグニチャーのように頻出するスピード感のある編集の連続を見た時からその不真面目さに大笑いしていたのだ。
作品は時間の流れとともにエクストリームな演出が頻出するようになる。しかし、ここではこの奇妙な作品のあらすじや物語の委細について、精神分析ジャンキー的に話すことに終始したくはない。むしろ、目を向けるべきはこの作品が「QUEER」という原作小説のタイトルのまま映画化されたことにある。バロウズの原作が執筆された当時、クィアという言葉には侮蔑的な意味が強く含まれていた。しかし、そういった意味合いがあるからこそ、それを自称することによって彼らが多義的で流動的な自己を主張することをも可能にしたのだ。そうした言葉が本来持つ意味に真摯に向き合ったこの映画が2024年というドナルド・トランプが政権をとった年に公開されたという事実も偶然か必然かこの映画が持つ可能性を拡大させていく。
知らず知らずのうちにカテゴライズされ、固定化されたクィアという言葉を、しがらみや過剰なまでの欲望、中毒、そして不可解性に引きずりこみ、泥に塗れた侮蔑語としての意味に回帰させる。しかし、同時にそれらの埃かぶった鉤括弧からクィアを解放し、流動性に満ちた存在だと示したことがグァダニーノがこの作品で成し遂げたことの一つだろう。
ここまでの話だけを聞いた人は、この作品のことを、さぞ社会的な意識の元に導かれた作品なのだろうと夢想するに違いない。しかし、彼は自分がこの作品を社会的な大義のために作ったと思われることには嫌気がさしてならないはずだ。なぜなら、この作品は彼のフィルモグラフィの中で、彼にとって最もパーソナルな映画だからだ。10代の頃に原作小説であるバロウズの「Queer」を読んで感銘を受けたグァダニーノは、いつか自身の手でこの作品を映画化することを夢見ていたという。グァダニーノはここで描いたものこそが映画で語りたい、自分自身の真実だとも言っている。
つまり、それは欲望を描き続けるということ、それは欲望の官能的な側面だけを描くことの限界に触れることでもある。年齢差を伴った恋愛における権力構造や、人間の精神と身体の不可逆的な乖離など、多くの人々にとって禁欲的であることが理想とされる所以とも言えるような、欲望の持つ負の側面を真面目に描ききったということ。これこそが最も今作で評価されるべき点なのではないだろうか。
2010年代後半以降に標榜された、アクティビズム的な潮流からは取りこぼされてしまったクィアという言葉の持つ流動性や、いわばそのだらしなさを掬い上げて描いたのだ。いうなれば、グァダニーノは生真面目にクィアの不真面目さと向き合ったということだ。LGBTQという言葉が世間に流布した今日において、その言葉がジェンダーやセクシャリティをお誂え向きのウェルメイドなワードローブに包みこんでしまうとすれば、グァダニーノはむしろ、全てをむきだしにさせ、その醜いまでの肉体を交差させることに成功したのだ。それは、これからの彼の作品の中で見られるか定かではないくらいに一過性のものなのかもしれない。この映画自体も映画的な作られ方はしていない。そう、映画的フォーマットに対しても、この映画はどこまでも不誠実でありクィアなのだ。ならばもちろん一貫性やスタイルなどはあるはずもなく、そこにあるのはただひたすらにだらしないだけのロマンスだ。真面目に不真面目であり続けることのために、「I’m not queer.」 「I’m disembodied.」なのだ。
Text: 田中柊