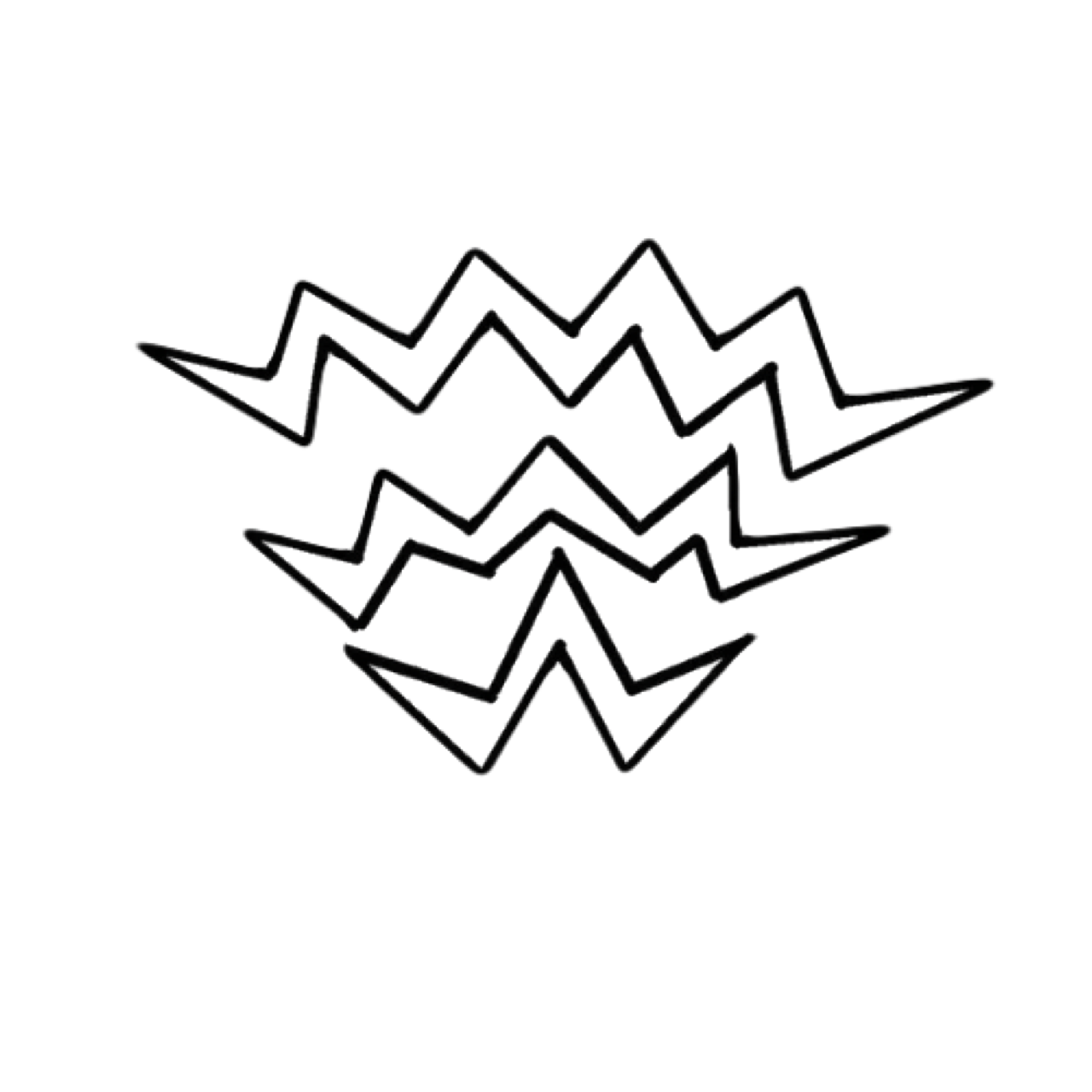Suchmosの再始動という祭が終わる頃に。
帰ってきたSuchmosは祭だ。
以下蛇足である。蛇足であるから重要である。
今イギリスをはじめとして、世界中はOasisの再結成ツアーというお祭りの最中にいる。それどころかアメリカではClipseという別の兄弟の帰還に熱狂し、BLACKPINKというK-POPのメガグループの再集結も、大きな話題を呼んでいる。
いわば2025年という年はお祭りの年なのだ。それはここ日本でも同じかもしれない。つまりはSuchmosの再始動のことだ。
2021年に活動休止を発表した彼らは、その後のシーンにも大きな足跡残した。もちろん、彼らの残したサウンドはCITY POPリバイバルなんていう見当違いなシティボーイたちのファッションアイテムとしても機能した。CityなんかよりTownだろ。そんな彼らのサウンドに影響を受けた後進のバンドがいくつも現れ、日本の音楽シーンは明らかにファンクやR&Bの要素を取り込んだポップスを量産した。その間も、彼らはそれぞれのトライブを見つけ各々での活動に精を出していた。田畑を耕すものもいた一方でど真ん中のPOPアーティストを支えるギタリストとして活躍するものも。
そんな期間を経て彼らは突如帰ってきた。そう祭の始まりだ。
彼らの新曲「Whole of Flower」は、その祭りが全ての契機であることを知らせる合図だった。
彼らの足跡をなぞるようにして、リバイバルという形でシティポップが隆盛を極めたことに対する、自己批評性に満ちた、ドンピシャのシティポップサウンドは、リバイバルではなくコピーなのである。いわば真打登場とでもいうべきサウンドだ。そして何よりも詞の中で執拗なまでに、この祭りがただの非日常などではなく、日常と地続きなもの、そう、日常を変化させる契機なのだと歌っているのだ。日が沈み、月が昇る。そうして初めて時は動き出し、血が巡っていく。祭りとともに私たちの日常が改めて始まり直すのだ。
さらに、他の新曲はどれもが、通底して残された者たちによる者であると感じさせるのだ。
これも祭りだ。祭りとは、生きたものによるものだ。死者に対する弔いや、思いを馳せる行為が含まれるのもこれが故だ。生きたものにしか行えないのが祭なのだ。それが死者にできないことであるというのを、彼らは強く意識している。だからこそ、彼らの音楽は祭だ。冠婚葬祭であり、祭祭祭祭であるのだ。
しかし、本当に大事なのは祭よりかはその後の生活の方にある。非日常とも思える経験をした人々はその帰路の中で、祭がない世界に戻っていく人と、祭が終わった後の世界に戻っていく人がいる。それは興行的な側面でも、産業的な側面でも非常に重要だろう。そうした後の世界を想起することもせずに、ただ刹那的に行われる祭りも中にはある。だからこそ、この先の我々は、何もなかった世界を進むのか、それとも、それを超えた先の何かに向かう世界を歩むのか。すでに選択肢は我々ではない何かに委ねるべきかもしれない。しかし、私は悲観的ではない。そしてSuchmosも悲観的ではないはずだ。なぜなら、これは単なる非日常ではなく、日常を変える、大きな一つの契機だからだ。そして、そうした希望を持つことこそが現代においてパンクであると思うから。悲しみは消え去ったわけではないが笑おうとするのだ。我々は我々の足でここまできたのだから。我々が決めていくのだ。
20世紀は人類の夏がとても短く終わることを知らせた(よって私は夏の本当の暑さ知らない世代の人間だ)。先に終わらせなかった課題は、まだまだ山積みどころか、雪崩のように我々に迫ってきた。21世紀に入り、10年代には正式に夏の終わりが観測されたはずであった。しかし、最後にもう一度花火を見ようと夏に縋る気持ちも、たしかに、この祭には詰まっているように思える。
ただ、私が今考えたいのは、この祭りが終わった後、私たちを待ち受けているのが、ただ怖いだけの時間に帰路を急ぐことなのか、はたまたそのエンジン音に身を委ねた、妖しくも新たなエネルギーを見つけ出す期待感なのか。祭りの後にこそ人々は動き出すはずなのだ。そんな契機を、期待を、私はSuchmosに向けている。
文:田中柊