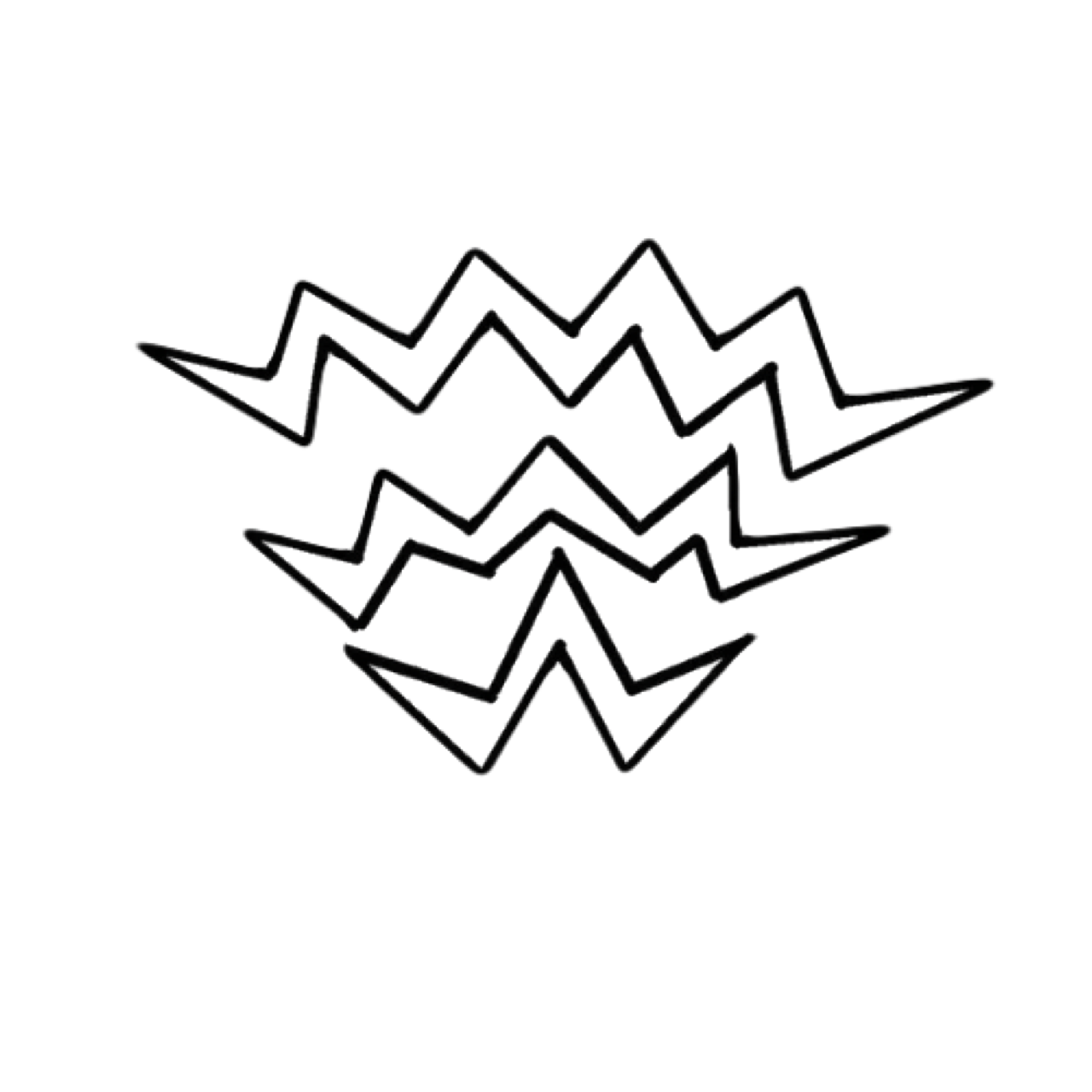何者からも自由でいて闘い続けられるか?〜ワン・バトル・アフター・アナザーと一本道〜
いつからだろう。倫理や政治が、芸術よりも偉くなったのは。客観的事実でもなければ、そう見るべきだ、なんて指南したいわけではない。だからというわけではないが、この文章の中で、誰かの名前を借りて、いかに自分の主張が正しいかを伝えるつもりは毛頭ない。なぜなら、ただそうしない方が面白そうだ、というだけだ。そうすることで私は隷属からの逃走(闘争)の中に生きることができるのだ。
ポール・トーマス・アンダーソン(以後PTA)の最新作「ワン・バトル・アフター・アナザー」は芸術だ。それは非常に多岐にわたる意味においてそうだった。アテンションエコノミーの中に青春を置いている我々世代にとって、芸術はもはや、何かを標榜するためのメディアに成り下がっていたともいえよう。アーティストは誰かの代弁者や、救世主、ひいては非人間的な偶像とされ、もはや何を発するかよりも、どのポジションから発しているかを明確にすることのほうが重要視されているとも思える。つまり、我々の誰もが、誰と同じ場所に立って誰に対してモノを言うのかを強要され、ジャッジされ続けている。
しかし、PTAはそれを拒否できた。「ワン・バトル・アフター・アナザー」は左派への美化されすぎた憧憬や、冷笑なんかにも収められない。トランプ批判なんてものでもない。むしろ、惚れ惚れ(飽き飽き)するまでのバランス感覚を擁している。
ちらほらと見かけるのがこの映画に対してのレヴューで、「これはドナルド・トランプに対する猛烈な批判である!」という言葉だ。しかし、ひとえに言えるのは、たとえば、レーガンでも、トランプでも、ニクソンでも、ブッシュでも、きっとその誰がそこの席にいようとも、彼はこの世界にこの芸術を生み出しただろう。現政権に対する批判なんていう目先にある対象に向けてこの作品は撮られたのではない。
そんなことよりも彼がしたのは、ただとにかくカメラを動かし、人の動き、物の動きを撮り続けただけなのだ。
それなのに、いやそれだからこそなのか、私たちはそこに映る芸術に感嘆する。
映画はカメラの動きや人と物の動きだけで2時間楽しめる。3時間楽しめた。これだけでいい。むしろこれが全てを語りうる力を持っている。この映画はそんな赤子にしかないような全能感を甦らせる。(と同時に、そんな素晴らしい産業が地平線に飲み込まれそうなことに嘆きたくもなった。)
この映画のどのプロットにおいてもカーチェイスは最高だ。どれも新しい。しかしどれも我々の知っている映画の興奮がみなぎる。逃げているのに闘っている。ガソリンの匂いがする。決して上手くないのに秀逸なカーアクションだ。
ボブは逃げている。しかしそれと同時に存在しない父親として娘を追っている。ウィラは逃げている。しかし存在しないはずの母親の影を図らずも追っている。ロックジョーは追っている。しかし同時に存在してはならない現実から逃げている。逃げながら闘い、闘いながら逃げる3人のカーチェイスは、遥か遠くまで広がるフィルムの一本の道の中で時間的な隔絶を超越し交わり続けている。画面に映るのは人とものの動く姿だけなのだが、一つ印象に強く残るのは、右にも左にもくねりながら続いていく一本の道なのだ。
話を戻すと、芸術は政治のためでも、倫理のためでも、正義のためでもない。宗教のためでもない。ただ人を人たらしめるものとしてそこにある。(しかし、今の世界では政治的じゃないという政治性すらも付与される。)
そう、それだけなのだ。なのになぜそれを何かのために奉仕させてしまうのだ。そんな近視眼的な矮小化の先にあるのは、あろうことか、愛すべき芸術を何かに隷属させる結果だろう。
この数十年でポップカルチャーが失ったのは、そうした知性の地平や強く語りかけうる言葉だろう。目の前のものを語らいすぎるがあまり、この果てしない世界について、理想を語る力を捨ててしまっている。つまり芸術の、いや人間の持つ美しさを、狭い狭い現代のアテンションエコノミー的牢獄に囲い込んでしまっているのだ。
闘っているようで逃げていて、逃げているようで闘っている。キャッチコピーそのままだが、彼はこの作品にそれをつけたのではなく、この作品でそれを成した。映画作家としての目先のポジション誇示や、政治的イデオロギーなんかからの逃走を図り、それよりも、もっともっと遙か先の未来にカメラを向ける闘争をしている。
ましてや、PTAは今作の製作に今までで一番巨額の予算を要している。そんな作品の中でこそ、彼は隷属や奉仕からの逃走(闘争)に身を投じた。まさにフィルムの中に広がる、遥か先まで乾き切った一本道の中を走り抜けるキャラクターたちのように、映画という産業の乾き切った道の中で彼は逃走(闘争)を続けてみせた。この逃走の次の闘争まで、せめてもの明るさが地平線に目視できることを願って。私たちはその消えゆく眩さに語りかけ続けてみよう。
文:田中柊